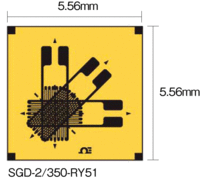歪ゲージの落とし穴:正しい測定結果を得るためのポイントをつかむ(2/3 ページ)
歪ゲージを使った歪測定は、一見すると単純な作業に感じられる。しかし、実際には、電気や物理、材料といったさまざまな分野の知識を必要とする極めて複雑なものである。本稿では、歪ゲージによる測定を行う際に考慮すべきポイントについて解説し、より正しい測定結果を得るためのノウハウを提供する。
なぜ困難なのか
歪ゲージを使っての測定は、“接着して測るだけ”の単純で簡易な方法だと見られがちである。しかし、実際には応力、荷重といったさまざまな項目を考慮しなければならず、多方面の知識を要求されるものだ。
歪ゲージを適用する際の最大の問題は、考慮しなければいけない項目が非常に多く存在するということである。電圧計や光センサーでは、メーカーによって精度がほぼ保証されている。そのため、測定を行うには、電圧プローブを回路に接続するかセンサーに光を当てるだけでよい。一方、歪ゲージを使った測定では、数百から数千に上る種類の中から最適な歪ゲージを選択するところから始めなければならない。歪ゲージを選んだら、場所を決めてゲージを被測定部品に接着する。接着する際には、接着するエリアを磨くという作業も必要になる。歪ゲージと測定に用いるアンプの接続も行わなければならない。しかもこれらの作業だけでは終わらず、ゲージの動作温度範囲を満たしているか、ゲージの出力を線形化したか、被測定部品における応力と歪の関係を完全に把握できているか、といった基本的な条件も確認する必要がある。
■応力の問題
グラスファイバやカーボンファイバなど、異方性、すなわち測定の方向によって特性が異なる材料が存在するという問題がある。通常、ファイバ系の材料はある一定の方向を向いた構造を成しているが、応力と歪の関係は、力を加えた方向と材料内部の方向との間の相互作用に依存する。異方性を持つ材料の歪を測定する場合には、2方向または3方向の歪を同時に測定できるロゼット歪ゲージを用いることになるだろう(写真4)。
歪ゲージを用いた測定において問題になることとして、被測定部品に存在する拘束応力が挙げられる。これは、制御が不可能で面倒な変数である。部品を固定し、レンチで位置を調整すると、その部品には多大な応力がかかり歪が生じる。そのような状態で歪ゲージを接着すると、たとえその部品が壊れる寸前であっても、あるいはレンチで調整したときに曲がってしまっていたとしても、歪は発生していないという測定結果になるだろう。
Hardy社のCornwell氏は、「正確な測定にはゲージが重要だが、それを配置するために使う工具の素材(鉄やアルミニウム)はもっと重要だ」と指摘する。その上で同氏は、線形性やヒステリシスの問題を避けるために、特殊な合金を使用することと、加工後の部品に加熱処理を行うことを提案している。こうした対処を施すことにより、加工処理による局所的な応力を緩和することがその狙いである。
また、歪ゲージは、ある領域の歪の平均をとって結果を出力する。ゲージの近くに穴があると、そこに応力が集中して大きな歪が生じるが、平均をとってしまうが故に、低い歪値を示してしまう場合もある。Vishay社のシニアアプリケーションエンジニアであるTom Rummage氏は、「観測している歪領域または応力の集中に応じた適切な長さのゲージを選択する必要がある」と述べる。
さらに微妙な問題も生じ得る。例えば、鋳物は表面が先に硬化し始め、内部は後から冷えて収縮しようとする。このとき、外部には内側に引っ張られて縮もうとする力が、逆に内部には外側に引っ張られる力が残ってしまい、残留応力(内部応力)が生じる。鋳造や溶接、加工などの過程を経た部品には、2次的または3次的な影響を軽視できないほどの静的な内部応力が存在していることは、覚えておかなければならない。
Rummage氏は、「自由境界には応力は存在しない。3個の歪ゲージを、穴を開ける個所から一定の距離をとって配置するケースを考えよう。この穴の存在により自由境界が生成される。そこにゲージが引き込まれるならば圧縮していたことになる。反対に、穴から遠ざかるようであれば張力が働いていたことになる。3個のゲージと、互いの角度の関係を理解すれば、部品にかかっている残留応力を計算することができる」と述べる。部品の残留応力が確認できれば、それを考慮した設計が可能になる。例えば、加熱処理、別の鋳造合金の使用、部品のどの部分にも弾性限界や疲労破壊の条件に触れる歪が存在しないことを確認するための測定の導入などがある。複数の鋳型、異なるプロセス、採用実績のないベンダーの製品を使用していないことを確認する。これらは内部応力のばらつきをもたらし得るからだ。しかしそのようなばらつきがあっても、例えばプレストレストコンクリートであれば、既存の内部応力によって荷重に対応するため、まったく問題がない可能性もある。
■荷重と放電の問題
測定の対象とする静的荷重/動的荷重についても知っておかなければならない。測定する歪に合ったゲージを選択するのは当然だが、衝撃荷重や運動量(モーメンタム)の影響、集中荷重なども考慮に入れる必要がある。静電放電によってセンサー部分が破損しないことも確認しておきたい。Hardy社のCornwell氏は、次のように述べている。
「ヨーロッパの安全規格であるCE(Conformité Européenne)に適合するよう設計されたフォークリフトがあったとしよう。ある工場でそのフォークリフトが稼働しているとすると、その周囲にいる人は、CEの規定よりもかなり高い電圧の影響を受けることになる。オペレータが荷台を重量計の高さまで下ろすと、フォークリフトのツメ(フォーク)から大きな放電が生じる。オペレータがアース用ストラップを使用していない場合、グラウンドからの帰還経路はロードセルと歪ゲージの配線を通る経路しかない。また、歪ゲージは、大きな歪を何度もかけると疲労破損する恐れがある。材料に圧力がかかった状態と張力がかかった状態とでは、弾性率が異なるかもしれないことも覚えておいてほしい。歪ゲージを扱うエンジニアは、材料、電子部品、力学(物理学)についてあらゆる理論を理解しておくべきなのだ」。
■設計と測定手順の問題
歪ゲージによる測定では、設計(設置)や測定手順によって大きな影響が生じる可能性がある。そこで、歪ゲージベンダーのアプリケーションエンジニアに協力してもらうというのも1つの手だ。例えば、米OMEGADYNE社の場合、長年の経験に裏付けされた専門知識を持つ同社のエンジニアらが、手順や設置についての疑問に答えてくれる。同社の設計および製造エンジニアであるWilliam Hamilton氏は、「われわれは、2週間ほどの短い期間でゲージをカスタマイズすることもできる」と述べている。
歪ゲージによる測定を甘く見てはならない。部品にゲージを適当に貼り付け、1時間ほどで測定結果を出すことも可能ではあるが、そのようにして得た結果はまず間違いなく誤っている。急いでいるときには、5分で固まるエポキシ系接着剤でゲージを接着したいと考えるのは自然なことだ。しかし、このような速乾性のエポキシ系接着剤は、凝固するときに熱を放出したり、収縮したりする。それによりゲージ自体に歪が生じ、誤った測定値が得られてしまう。同様に、箔ゲージをエポキシの分厚い塊に取り付けてはならない。接着剤を厚く塗りすぎると、箔ゲージと部品表面の間にすき間ができてしまい、大きな測定誤差が生じるからだ。測定したいのは部品の歪であり、部品とゲージのすき間の歪ではないのである。
測定の際には、歪ゲージの選択と設置が正しいことを検証するための実験を行うことをお勧めする。OMEGADYNE社のOEM販売マネジャを務めるRob Carney氏は、「われわれの顧客が抱える最大の問題は、いかにして適切な歪ゲージを選択するかということだ。選択に当たっては、精度、安定性、温度範囲、伸張性、テスト時間のすべてが重要な要素となる」と述べる。歪ゲージを設置したら、測定値がきちんとゼロにリセットされることやヒステリシスがないこと、再現性が高いことを確認してほしい。なお、測定はNIST(National Institute of Standards and Technology:米国標準技術研究所)の規格に合わせて行う必要がある。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.