進化するIoTエッジノード開発の「最適解」〜単一プロセッサの組み込みシステムからの脱却〜:I3C活用が鍵に
IoTデバイスの進化に伴い、エッジセンサーノードには更なる高性能化と省電力化が求められている。この両立にはシステムを速度領域ごとに分割し、高速プロセッサとアナログサブシステムを効率的に接続する設計が求められ、高速チップ間通信の業界標準となりつつあるI3Cの導入がその鍵となる。本稿では、Microchip TechnologyのMCU部門担当副社長を務めるGreg Robinson氏が、デジタル領域での高性能化とアナログ精度の両立を可能にする設計手法と、そのためのMCU選びの重要性を解説する。
インターネット接続によって高まる処理要件
組み込みシステムは、かつてないほどのペースで技術進化を遂げています。家庭や車、職場の機器は機能面で飛躍的な進歩を続けています。この目覚ましい進化の要因として真っ先に挙げられるのは、ほんの小さな電子機器までもが現代のネットワークインフラに接続できるようになった事です。Wi-Fi、Bluetooth等の接続技術により、フィールドでのアップデートや保守が容易に実行できるようになり、AIや機械学習アルゴリズムの恩恵も受けられるようになりました。このような接続性の向上により、これらのデバイスは実質的にIoTエッジノードとなります。しかし、それと引き換えにネットワーク接続に伴う処理能力の向上とメモリサブシステムの拡大が必要になります。
アナログ世界をクラウドに、そこで生じる新たな課題
ほとんどの組み込みシステムは周囲の環境にも「つながって」います。周りの環境をセンシングしたり、何かを物理的に動かしたりする機能、またはヒューマンインタフェースのための機能を備えています。例えば、スマートサーモスタットは人間が入力するためのボタンや静電容量式センサーを備えているだけでなく、温度センサーや湿度センサーのローカルネットワークにも接続されています。また、ネットワークに接続された調理家電の主な役割は、食品に対する調理に最適な温度情報を取得し、それを元に熱量を正確に調整する事です。こうした主に「アナログ」なシステムが急速に進化するクラウド通信の世界に組み込まれる事で、新たな課題が生まれています。ゆっくりと変化するアナログ世界の入力に対応するようにシステムを最適化すべきか、それとも処理速度や全体の機能向上を優先してアナログ精度を多少犠牲にするか、という選択です。この課題を深く理解するために、この種のアプリケーションで一般的かつシンプルな例としてIoTエッジセンサーノードを見ていきましょう。
アナログサブシステムに求められるもの
IoTエッジセンサーノードには、温度、湿度、動き等の環境条件を計測および監視するアナログサブシステムが必要です。このアナログサブシステムには、センサーデータを読み取り、処理し、ネットワークで通信するMCU(マイクロコントローラー)が含まれます。一般的に、環境データは緩やかに変化するため、ほとんどのエッジノードは連続的なデータストリームを絶え間なく処理する必要はありません。エッジノードは数年間バッテリーの交換なしで動く事が多く、通常は低消費電力の「スリープ」モード状態にあり、環境の変化を検出するために時々復帰します。復帰すると、データを収集してネットワーク経由で送信します。その後、次の計測まで再びスリープ状態に戻ります。世の中が高度に接続され、エッジノードの数と収集するデータの量が増加し続ける中、アナログサブシステムのバッテリー寿命を延ばすには、電力効率と低消費電力動作が設計上の重要ポイントとなります。
組み込みシステムのセグメント化
組み込みシステムを効率化するには、システムを別々の「速度領域」にセグメント化して、高速なメインプロセッサと高速性を必要としないアナログサブシステムをブリッジでつなぐのが最も効果的です。システムを分割する事で、アナログサブシステムが変化の緩やかなタスクを担当し、高速メインプロセッサが高速かつ演算負荷の高い処理タスクを担当できるようになるため、それぞれのシステムの強みを最大限に生かす事ができます。
接続デバイスの数が増え続ける中、高速なチップ間通信を実現する次世代のシリアル通信インタフェースとしてI3Cが注目されています。I2Cの後継であるI3Cは、より高速かつスマートなインタフェースと高度な制御機能を提供し、将来のアプリケーションに最適です。I3CはI2Cデバイスとの下位互換性を維持しているため、既存のハードウェアプラットフォームにも簡単に導入できます。
また、I2Cデバイスは12.5MHzで動作するI3Cコントローラーと共存できるため、既存のI2Cバス設計からI3C仕様への移行も可能です。例えば、I3CとI2C、SPI、UART等のレガシー通信インタフェースをサポートするMCUをブリッジデバイスとして使う事ができます。このブリッジは、高速プロセッサと低速なセンサーをMCU経由で接続します。MCUはセンサー入力を計測し、結果を計算して効率的にデータを転送します。この構成により、I3Cバスの整合性と速度を保ちながら、MCUを介してI3CコントローラーとI2C/SPIデバイス間の通信が可能になります。組み込みシステムを分割し、I3Cの機能をフルに活用する事で、システム設計を効果的かつ堅牢に実装できます。
I3C対応MCUファミリー「PIC18-Q20」
Microchip社では、最新の分散型プロセッサ組み込みシステム向けに「PIC18-Q20」製品ファミリーを開発しました。これらのMCUは、最大2つのI3C周辺モジュールを含む先進のシリアル通信インタフェースを搭載しており、複数のバスへの高速接続を実現して柔軟性を高めています。
また、UART、SPI、I2C、SMBus等のレガシー通信プロトコルも組み込まれているため、ブリッジデバイスとしてシームレスな統合を実現でき、I2C/SPIクライアントデバイスを純粋なI3Cバスから分離できます。この構成により、I3Cバスの速度を維持しながら、I3CコントローラーがMCUを介してI2C/SPIデバイスと通信できます。さらに、PIC18-Q20は複数の電圧領域間の接続にも対応しているため、動作電圧レベルの異なるさまざまなコンポーネントに簡単に接続できます。これによりレベルシフターが不要になり、部品コストを減らしシステム設計を簡素化できます。
PIC18-Q20には、CPUに頼らずに動作し、他の周辺モジュールと直接通信できるCIP(コアから独立した周辺モジュール)が内蔵されています。これらのハードウェアを基盤とした周辺モジュールは、消費電力を最小限に抑え、同等の機能をソフトウェアで実装する場合と比べると、ほとんどもしくは全くコードを必要とせず、RAMやフラッシュメモリの使用量を大幅に削減できます。そして、多くの機能を1つのMCU内で同時に実行できます。設計者は、MCC(MPLAB Code Configurator)というシンプルなGUI(グラフィカルユーザーインタフェース)環境を使って、I3C周辺モジュールを含むCIPの組み合わせを簡単にカスタマイズでき、データシートを通読しなくてもアプリケーションコードを生成できます。CIPにより、エンジニアはシステムタスクを分割して管理しやすくなり、部品点数、コードサイズ、開発期間、消費電力を削減できます。
まとめ
急激に変化する現代では、技術革新によって処理の高速化、接続の高速化、そして小型化への要求がますます高まっています。現代の電子機器は外部世界とのつながりが日々増加しています。こうしたコネクテッドなシステムにおいて「現実世界」を感知し計測するには、小型でエネルギー効率の高いアナログサブシステムが必要です。環境データの変化は通常緩やかであり、その設計目標は高速化への要求とは相反する方向性にあります。
効率的な組み込みシステムを実現するには、システムを複数の速度領域に分割し、ブリッジを使って高速プロセッサをアナログサブシステムが存在するシステム周辺部分に接続する事が有効です。I3Cが高速なチップ間通信における事実上の業界標準インタフェースとなりつつある今、エンジニアにとって重要なのは、デジタル領域での高性能化の要求に対応しながら、同時に次世代設計で高いアナログ精度を維持できる先進のMCUを選択する事です。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
提供:Microchip Technology Inc.
アイティメディア営業企画/制作:EDN Japan 編集部/掲載内容有効期限:2025年6月19日
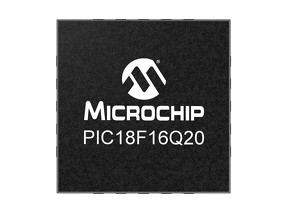 分散型プロセッサ組み込みシステム向けに開発されたI3C対応MCUファミリー「PIC18-Q20」提供:Microchip Technology
分散型プロセッサ組み込みシステム向けに開発されたI3C対応MCUファミリー「PIC18-Q20」提供:Microchip Technology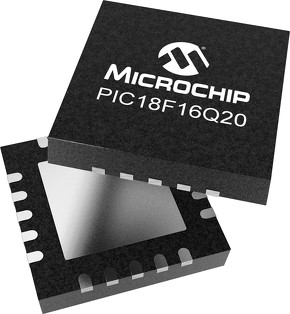 PIC18-Q20は、I3Cおよび複数の電圧領域対応、CIPなどの各種機能によって、IoTエッジノードにおける課題を解決する 提供:Microchip Technology
PIC18-Q20は、I3Cおよび複数の電圧領域対応、CIPなどの各種機能によって、IoTエッジノードにおける課題を解決する 提供:Microchip Technology