TDT/TDR測定とシミュレーションの連携(1/3 ページ)
デジタルオシロスコープによってTDT/TDR測定を行った結果から、ケーブルやバックプレーンなどのSパラメータモデルを構築する手法を紹介する。このようにして作成したモデルを用いたシミュレーションの結果は、実機での測定結果とよく一致する。実際、筆者らは、新たなデバイスを設計する際に、この手法を日常的に活用している。
IC設計者やサポートエンジニアは、データチャンネルの実用的なモデルを作成し、そのモデルによって信号伝送を正確にシミュレーションしたいという場面にしばしば遭遇する。データ転送速度が低ければ、コネクタやビア、伝送線路などをSPICEモデルで表現してシミュレーションすることができる。しかし、データ転送速度が10ギガビット/秒ほどにもなる高速な信号の場合、SPICEモデルではシミュレーションの実行時間が長過ぎ、また実際の測定値とシミュレーション結果が整合しなくなってしまう。
実用性の高いモデルが必要
IBIS(I/O Buffer Information Specification)に代表されるビヘイビアモデルを使えば、シミュレーションを高速に実行することができる。また、プリエンファシスを含む複雑な信号の伝送線路を正確にモデル化することも可能だ。ただし、モデルベースの手法である限りは、シミュレーションの結果と実際のデバイスの動作を整合させる必要があることに変わりはない。
本稿では、デジタルサンプリングオシロスコープ(DSO:Digital Sampling Oscilloscope)によって取得した信号波形をベースにしたシミュレーション手法について述べる(図1)。時間領域の信号をフーリエ変換した結果、得られるデータと、TDT(Time Domain Transmission)測定から得たS(Scattering)パラメータを組み合わせることで、複雑な配線システムを伝送される信号をモデル化しようというものだ。これを利用すれば、例えば、システムの実際の応答に基づいて作成したデータパスのライブラリを使い、新たに設計した出力ドライバ回路の動作をシミュレーションで求めるといったことが行える。システムにその出力ドライバ回路を組み込んだ際の動作を、シミュレーションによって迅速に把握することも可能になる。
Sパラメータの算出方法
まず、1つの具体例を用いて、Sパラメータを取得する方法を説明する。その例とは、フリップチップBGAパッケージに封止した非同期クロスポイントスイッチICが備える入出力ポートのSパラメータを取得する作業である。筆者が所属するVitesse社は、ユーザーからの要求に対応するためにこの作業を行うことになった。そのときには、あいにく4ポートのベクトルネットワークアナライザ(VNA:Vector Network Analyzer)を利用できなかった。そのため、Vitesse社のアプリケーションエンジニアは、いくつかの手法を試みることになった。
最も簡単そうに思えたのは、米Synopsys社のSPICEシミュレータ「HSPICE」を用いてTDR(Time Domain Reflectometry)テスト環境を構築することであった。HSPICEは、よく知られている伝送線路解析用回路モデル「Wエレメント」を備えている。このHSPICEによるTDRのシミュレーション結果が、TDR測定の結果とよく一致するまで、複数のセグメントで構成される伝送線路モデルを調整するのである。これは時間のかかる退屈な作業だった。しかも、SパラメータのS11は、実際の入力に対して“まあまあ一致する”というだけの結果に終わってしまった。
そこで、TDR測定の結果を直接的に利用することを考えた。すなわち、TDR測定の結果を高速フーリエ変換(FFT)し、S11を計算するのである。
この手法において問題になるのは、正規化処理と、ボードの影響の補償だ。これらについては、参考文献*1)、*2)に示した米EDN誌の過去の記事を参考にすることにした。正規化処理には、テストボードから取り外したBGA部品単体のTDR応答を利用する。
BGAのS11のパラメータは、次のような手順で得ることができる。まず、BGA部品を搭載したボードのTDR応答とBGA部品を載せない状態のボードのTDR応答を取得する。続いて、両方の結果に対してFFT処理を施し、周波数領域のデータに変換する。それからBGA部品を実装済みのボードのS11(複素数)を、部品なしのボードのS11で除算する。すると、BGA部品のS11が得られる。
TDR測定からS11を導けるのと同様に、TDT測定からはS21を導ける。これらのSパラメータを利用すれば、バックプレーンやケーブルなど、損失を伴う伝送媒体における信号伝送の様子をモデル化することが可能である。
シミュレーションの進め方
筆者らは、科学技術計算ソフトウエア「Scilab」を利用してシミュレーション環境を独自に構築した。Scilabは豊富な解析機能を備えるオープンソースのソフトウエアである。
シミュレーションはデータチャンネルのTDT測定とTDR測定の結果をベースとして実行する。ステップ応答波形からスティミュラス波形を取得することでシミュレーションや合成が行えるため、この手法は柔軟性が高い。シミュレーションでは時間領域のデータを周波数領域のデータへと変換し、簡単な算術演算によって正規化処理とボードの影響を除去する処理を施す。
構築したシミュレーションシステムでは、TDT応答のファイルをデータチャンネルのライブラリとして保存するようにした。このファイルには、TDTにおけるスティミュラス波形を直接測定することによって得た正規化済み取得値を盛り込む。
これとは別に、複数のラインドライバから取得した波形、あるいはラインドライバをシミュレーションした波形もライブラリとして登録する。その際には、プリエンファシスをかけた波形と、プリエンファシスなしの波形の両方を保存しておく。波形の種類は、ステップ信号または、PRBS(Pseudorandom Binary Sequence)信号である。
シミュレーションの典型的な進め方を図2に示した。データチャンネルのライブラリには、損失を伴うバックプレーンのTDT波形とTDT用のステップ信号源の波形を保存する。もちろん両者に使用するケーブルの組み合わせは同一である。これらの波形を複素周波数領域に変換し、比率を算出すると、データチャンネルの正規化されたS21(複素数)が求められる。
データチャンネルの励起には、測定によって取得済みのPRBS波形あるいは出力ドライバモデルのシミュレーション波形を使う。時間領域の信号波形を周波数領域に変換し、これに正規化済みのチャンネル応答(すなわち、S21)を乗じる。このようにして得た周波数領域の応答を時間領域に変換すると、信号波形やアイパターンが得られる。
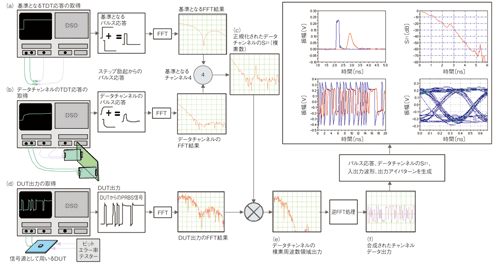
図2 シミュレーションの進め方 ステップ信号源のTDT測定(a)とデータチャンネルのTDT測定(b)を実施した後、両者の測定結果をFFT処理し、S21を計算によって求める(c)。DUTのPRBS応答を測定し(d)、FFT処理してから、S21を乗じて逆FFT処理し(e)、データの出力波形を合成する(f)。
脚注
※1…Pickerd, John J, "Impulse-response testing lets a single test do the work of thousands," EDN, April 27, 1995, p.95
※2…Smolyansky, Dima, "Signal-integrity modeling of gigabit backplanes, cables, and connectors using TDR," EDN, July 11, 2002, p.63
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.