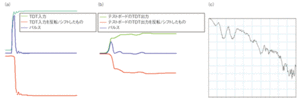TDT/TDR測定とシミュレーションの連携(2/3 ページ)
デジタルオシロスコープによってTDT/TDR測定を行った結果から、ケーブルやバックプレーンなどのSパラメータモデルを構築する手法を紹介する。このようにして作成したモデルを用いたシミュレーションの結果は、実機での測定結果とよく一致する。実際、筆者らは、新たなデバイスを設計する際に、この手法を日常的に活用している。
TDT/TDRの測定環境
TDT波形の取得には、立ち上がり時間が35psのステップ信号源と帯域幅が50GHzの入力チャンネルを備えたDSOを用いる。一方、TDR応答の取得には、入力帯域幅が20GHzのDSOを使う。測定条件はサンプリング時間が20ns、平均化処理は128波形分、分解能は4000ポイントとする。この条件であれば良好な結果が得られる。なお、平均化処理で波形数を必要以上に多く使っても、測定結果はあまり改善されない。
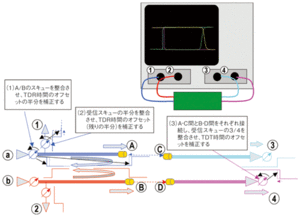
図3 TDTとTDRを整合させるプロセス まず、オープンケーブルのTDR信号を観測する。正相/逆相の相対的な時間を調整し、ケーブルコネクタA/Bの信号に整合するようにする。観測する信号はケーブル中を2回伝搬しているので、調整によって補正しているのはTDR時間のズレの半分だけである。TDRからS11を算出する場合は、残りのTDR時間のオフセットをTDR受信チャンネルで調整する。伝送チャンネルの整合が済んだら、AとCを接続し、BとDを接続する。接続には短いバレルアダプタを使う。それからチャンネル4とチャンネル3のスキュー調整機能を用いて、コネクタCとチャンネル3の間、コネクタDとチャンネル4の間を調整する。
差動測定では、ケーブル対をできる限り近くにそろえて配置する。それからDSOのスキュー調整機能を使い、DUT(Device under Test)のSMAコネクタのローンチポイントにおけるステップ位置を微調整する(図3)。開放端のケーブルに対するTDR測定では、SMAコネクタのローンチポイントに信号が到達するまでの伝搬時間が2倍になることを考慮し、差動TDRにおけるステップ信号のスキューを、開放端ケーブルのTDR波形の位置合わせに必要な時間の半分に調整しておく。S11を算出するためにTDR応答を取得する場合には、DSOの受信チャンネルで残り半分のスキュー調整を行う。この例では、チャンネル1のスキュー調整値からチャンネル2のスキュー調整値を差し引く。
TDT波形を取得するDSOの受信チャンネルにおいては、タイミングを合わせ込むことも重要になる。ローンチケーブルの応答を整合させたら、SMAバレルアダプタを用いてローンチケーブルをレシーバケーブルに直接接続し、TDT受信チャンネルのスキューを合わせる。タイミングのズレは、2ps以内が目標である。ただし、正相の波形と逆相の波形が完全に対称になることはないので、この目標を達成するのはかなり難しい。実際には20psくらいのズレがあっても、取得するスティミュラスデータと応答データでズレが一定ならば、計算結果に大きな影響が及ぶことはない。
TDT/TDR波形の取得
ローンチケーブルとレシーバケーブルが接続されている間に、TDTスティミュラス波形を直接的に取得する。このTDT波形は、この後に出てくるデータチャンネルの測定値に対する正規化処理に利用する。
次に、DUTであるデータチャンネルを入力ケーブルと出力ケーブルの間に挿入し、TDT応答波形を取得する。なお、DSOによっては、タイミング情報を記録できない機種がある。その場合はデータファイルごとに期間幅についての情報を記録しておく。簡単なのは、ファイル名に期間幅を表す数字を使う方法である。
DSOで取得したステップ応答波形に対し、そのままFFT処理を施してはならない。「離散フーリエ変換で扱う信号で最悪なのは、ユニットステップ関数である」*3)からだ。例えばマイナス無限大の時間からプラス無限大の時間まで続く信号に対して離散フーリエ変換を行いたいとする。その場合、実際には有限の時間幅でデータを切り取ることになるが、そのデータの両端の値が異なると、周波数スペクトラムは大きく歪(ひず)んでしまう。
ステップ関数から得たインパルス関数のTDT応答や、ステップ関数に対するシステムのTDT応答であれば、こうした問題は生じない。ただし、実際には、ステップ関数を使った計算結果には計算上の誤差が含まれる。そこで参考文献1、3では、離散フーリエ変換の前に、ステップ応答を有限パルス応答に変換することを提案している。参考文献1ではステップ応答を反転したものを取得した波形の最後に付加し、期間幅の2倍の時間長のパルス応答を生成する方法を紹介している。一方、参考文献3には、ステップ励起から得られるパルス励起を利用する方法が示されている。
参考文献3を改良したのが、波形をきわめて短い時間(Δt)だけ遅らせて元の信号波形から差し引き、幅Δtのパルス応答を生成する方法である(図4)。この方法では、遅延させて差し引く信号の最初の部分、すなわちゼロからΔtまでの期間を初期値で埋め、それと同じ期間を最後の部分から切り取っておく。こうして、時間軸をずらす前の信号と期間幅をそろえる。
遅延させた信号データの周波数成分は元の信号データと変わらないので、Δtはどのような値でも構わない。例えばΔtを90ps未満の値にすると、Vitesse社の最高速クロスポイントスイッチの性能である11ギガビット/秒に適合する。得られたパルス応答により、符号(シンボル)間干渉(ISI:Intersymbol Interference)の影響を把握できる。この方法には、0V基準の信号を生成できるという利点もある。
パルス関数に変換された入出力波形から、複素パルス応答に対するFFT結果におけるスティミュラス成分に対するエレメント比率(Scilabの関数「./」で求める)としてS21を算出する。その際、正規化は自動的に行われる。図4(c)のS21は、米Agilent Technologies社のテストボードで取得したTDTデータから計算したものである。同様に、スティミュラス応答とTDR応答のFFT結果から、S11を算出できる。
脚注
※3…Andrews, James R, PhD, "Time-domain spectrum analysis and S-parameter vector network analysis," Application Note AN-16, Picosecond Pulse Labs, May 2004
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.