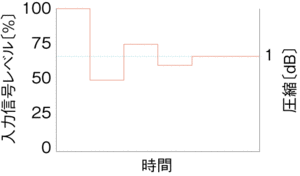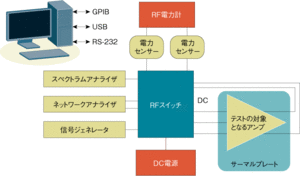RFテスト開発の現場:4社の事例で知る(1/2 ページ)
テスト装置が進化を遂げる一方で、RFテストの現場では、装置が備える専用の測定/解析機能を使用せず、アルゴリズムやテストプログラム、テストの自動化手法を独自に開発/使用しているエンジニアも多い。本稿では4社のエンジニアに対して行った取材を基に、それぞれがどのような理由で、どのような取り組みを行っているのかを紹介する。
独自に開発する理由
高周波用途向けのアンプ回路(RFアンプ)やRF ICなどのテストは、単調な作業の繰り返しになりがちである。RFデバイスは、広範にわたる周波数/電力レベルで動作する上に、当然、すべての動作温度範囲や電源電圧範囲において仕様を満たしていなければならない。こうしたすべての条件に対するテストを実施すると、かなりの量のデータが生成されるのは明白だ。テストを簡易化/自動化する機能があれば、テスト時間を短縮し、すべてのデータを有効に活用することができるだろう。
しかし、テスト方法を改善できるような最新の機能を持つスペクトラムアナライザやネットワークアナライザ、または電力計があったとしても、測定の対象となるRF ICが古い仕様のものである場合、その計測機器を使用することはできないかもしれない。逆に、最先端のRF製品をテストしたい場合には、必要な解析機能などをテスト装置が備えていない可能性がある。このような事情から、開発者はテスト手法/環境を独自に開発する必要に迫られることになる。
では、実際に、現場のエンジニアらはどのようなテスト方法を独自に開発しているのだろうか。これについて、筆者は4社のエンジニアに話を聞いた。以下、その内容を4つの事例として紹介する。
CASE 1 | 高い測定精度の確保
米L-3 Communications Narda Microwave East社のテストエンジニアBill Drago氏は、C帯域からKa帯域で動作するRFアンプ、周波数アップ/ダウンコンバータ、トランシーバの製造を支援している。Drago氏は、「この種の製品は、何年間も同じ仕様で製造が続けられる場合が多い。そのため、最新のテスト装置の機能を適用できないケースがある。新しい機能を使えば、測定が必須の項目の多くを自動化できるにもかかわらずだ」と述べる。同氏は自動化に役立つ新機能が提供される前に、すでに独自のテスト環境を構築していた。アンプのゲイン、1dB利得圧縮ポイント、IMD(相互変調歪)、反射損失、スプリアスノイズ、雑音指数などの自動測定を行うテストプログラムも開発した。
Drago氏は、スプリアスノイズのテストの重要性を次のように説明する。
「周波数コンバータには、LO(局部発振器)を用いる。このLOは、顧客の要求仕様に合わせて一定の範囲とステップサイズを設定する必要がある。また、コンバータは、対応周波数範囲において指定されたステップでプログラミングが可能な周波数シンセサイザを備える。周波数シンセサイザにより、コンバータにスプリアスが生じてはならないので、その点をテストする必要がある」。
Drago氏は、スプリアスノイズを測定するために、米Agilent Technologies社のスペクトラムアナライザを用いて、搬送波周辺のおよそ1GHzの帯域で周波数掃引を実行する。通常、同氏は、それぞれ601の周波数ポイントを含む複数の狭い帯域に分割して掃引を行う。すなわち、各ステップは数kHzの幅となる。仮に、広い帯域幅で1度に掃引したとすると、ステップサイズと計測機器のRBW(分解能帯域幅)が大きすぎるため、スプリアスを見落とす可能性があるからだ。また、同氏は、「狭い帯域幅で掃引を行うほうが、一気に掃引するよりも時間がかからないことが多い」と述べている。さらに、大きな掃引が完了するまで待つより、小さな掃引のほうが問題点を早く検出できる場合もある。
Drago氏が使用している何種かのスペクトラムアナライザの中には、スプリアスノイズを測定するための専用機能を内蔵しているものもある。しかし、同氏はそれを使用していない。その理由は、所有しているすべてのスペクトラムアナライザがその機能を備えているわけではないからだという。その代わりに、同氏は独自のテストプログラムを作成している。そのプログラムを用いたテスト環境を計測機器に外付けすることにより、どのようなスペクトラムアナライザでも使用できるというわけだ。
Drago氏は、RFアンプの1dB利得圧縮ポイントを測定するものなど、ほかのテストプログラムもいくつか作成している。同氏は、所有するベクトルネットワークアナライザの一部にこのテストプログラムを組み込んでいる。アルゴリズムには、逐次比較(SAR)型のA-Dコンバータで用いられるのと同様の2分探索(バイナリサーチ)処理を使用している。まず、Agilent社のRF信号ジェネレータにより、テストの対象となるRFアンプにおいて最大値となる入力信号を生成する。そして、出力電力をAgilent社のRF電力計で測定する。図1のように、1dB利得圧縮ポイントが検出されるまで、入力信号のレベルの上げ下げを繰り返していく。
CASE 2 | テストの汎用性を高める
米Comtech PST社は、500MHz〜6GHzの周波数帯、100W〜10kWの電力レベルで動作するRFアンプを製造するベンダーである。同社のテストエンジニアMichael Ford氏が頻繁に使用するテスト環境は、RF信号ジェネレータ、スペクトラムアナライザ、ネットワークアナライザ、電力計、RFスイッチ(RF‐DC切り替えユニット)から構成される(図2)。RFスイッチの制御は、米Measurement Computing社製のUSBデジタルI/Oモジュールで行う。そして、RFアンプは、温度を変化させるサーマルプレート上に配置する。このテスト環境により、ゲイン、出力電力、高調波歪、IMD、効率、スプリアスノイズを測定できる。
Ford氏は、計測機器が内蔵する機能を使用することもあるという。例えば、スプリアスノイズは、Agilent社のスペクトラムアナライザが内蔵する機能で測定するといった具合だ。しかし同氏も、計測機器に各種項目の専用測定機能がない場合には、独自のテストプログラムを作成して測定を行っている。
Ford氏は、設計と製造の両方をサポートしている。設計時に行う評価作業では、スプリアスノイズや高調波解析などについて、測定器が備える専用機能を使用する。一方、製造向けには、Ford氏は必ず独自のテストプログラムを使用する。「われわれはモジュラー形式の独自のソフトウエアルーチンを作成している。そうすれば、Agilent社やドイツRohde & Schwarz社など複数のベンダー製の装置を使用することができるからだ。計測機器のコマンドライブラリのみを変更して、同じテスト用ルーチンを使用している」と同氏は述べる。例えば、スプリアスノイズ測定用の同氏のルーチンは、どのメーカーのスペクトラムアナライザでも利用できる。
搬送波の高調波を測定するためにFord氏が作成したルーチンは、中心周波数、幅、RBW、VBW(Video Bandwidth:ビデオ帯域幅)といったパラメータを使用する。これらのパラメータが引き渡されたら、そのルーチンは、高調波電力を検出するために搬送波周波数の倍数で掃引を実行する。結果は、解析用にスプレッドシートに出力される。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.