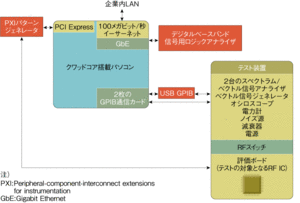RFテスト開発の現場:4社の事例で知る(2/2 ページ)
テスト装置が進化を遂げる一方で、RFテストの現場では、装置が備える専用の測定/解析機能を使用せず、アルゴリズムやテストプログラム、テストの自動化手法を独自に開発/使用しているエンジニアも多い。本稿では4社のエンジニアに対して行った取材を基に、それぞれがどのような理由で、どのような取り組みを行っているのかを紹介する。
CASE 3 | テスト/解析時間の短縮
Joe Flynn氏は、ファブレス半導体企業である米Sequoia Communications社のスタッフエンジニアである。同氏は、携帯電話用のワイヤレス規格を複数サポートするRF ICを評価しており*1)、そのためのテスト環境をいくつか開発している。トランシーバのゲイン、雑音指数、IMD、混変調、EVM(Error-Vector Magnitude)の各特性を評価するためのものである。Flynn氏は独自の自動化ツールも開発しているが、装置を選択する際に最も重要な要素は、テストにかかる時間であるという。
RF ICは変調信号を送受信するため、Flynn氏のテスト環境では、周波数成分を評価するためのスペクトラムアナライザを利用している。図3は、Sequoia社製ICのレシーバ用のテスト環境を簡略化して表したものである。このテスト環境により、基地局やほかの携帯電話機、ラジオ放送局などからの望ましくない遮断信号が存在する場合のレシーバの動作を評価することができる。
遮断信号テストの一環として、Flynn氏は100kHz〜12.7GHzの周波数範囲において200kHzステップでS/N比(信号対雑音比)の測定を行う。チャンネル当たり約6万回の測定を行わなければならないことに加え、RF ICには7つの周波数帯域上に1300のチャンネルが存在する。このように、S/N比のテストでは大量の測定データが生成される。
Flynn氏はデータ解析に利用するためのツールなども開発している。例えば、製造前の100個の部品に対するゲイン、反射損失、消費電流などのパラメータの分散を知りたい場合がある。「分散データを見れば、その部品がどのように動作するかという感覚がつかめる。開発したツールは、こうしたデータの解析に役立つ」と同氏は述べた。
Sequoia社は、テスト環境で取得した評価データを操作するためのツールも開発している。Visual Basicで作成したウェブベースのツールであり、「.netCharting」(http://www.dotnetcharting.com)というソフトウエアを使用して、部品に関する約1200個のグラフを作成するというものだ。Flynn氏は、「このツールを使えば、テスト結果のレビューを行う際、測定値が仕様を満たしていないケースを容易に検出することができる」と述べる。
Flynn氏は測定時間を短縮するために、2台のAgilent社製シグナルアナライザ「MXA」を、レシーバのI/Q各チャンネルに1台ずつ使用する。2台のスペクトラムアナライザの周波数と位相は同じ値に固定され、それにより測定の同期がとられる。次に、テスト時間を短縮するために、RBWと掃引時間を最適化する。「最初は、ある遮断周波数におけるS/N比を1回測定するのに、1チャンネルにつき約1秒かかった。今ではそれを18msで実施できるようになった」と同氏は述べる。
また、LANとGPIB(General Purpose Interface Bus)通信の両方を使用することでも、テスト時間を短縮できるという。「短いコマンドの列を送信する上で、GPIBは有利だからだ」(Flynn氏)。さらに同氏は、デジタルベースバンド信号のデータを収集するロジックアナライザにイーサーネットを使用する。加えて、専用のギガビットイーサーネットに対応したLANカードを使用して、テスト装置と企業内LANの間のパケット衝突(Collision)を回避している。同氏は、テスト装置全体で3枚のGPIB通信カードを使用している。
CASE 4 | 装置メーカーとの連携
ファブレス半導体企業である英CSR社は、BluetoothやWi-Fiなどのパーソナルエリアネットワーク向けワイヤレス通信に用いるRF ICを開発している。同社のアプリケーションエンジニアリンググループを統括するJames Blackwell氏は、顧客が同社のRF ICを評価し、そのICをベースとした製品を開発することを支援している。
CSR社のエンジニアは、社内で構築したテスト環境と購入したテスト装置を組み合わせて使用する。通常は、社内のテスト環境をまず使用する。Blackwell氏は「われわれは最先端にいることが多いからだ。テスト装置企業が追いつくまでの間は、独自のテスト環境を開発する必要がある」と述べた。
その1つが、ループバックテストを実行可能なBluetooth用テスト環境である。「Bluetoothの仕様では、テスト装置がDUT(Device Under Test:テスト対象デバイス)をワイヤレスに制御するループバックテストが定義されている」とBlackwell氏は述べた。このループバックテストにより、メーカーは製造ラインを移動するBluetooth製品をワイヤレスでテストすることができる。
CSR社のエンジニアらは、数年前にBluetoothに対応したRF ICを開発した。その際、RF信号ジェネレータ、スペクトラムアナライザ、ベクトル信号アナライザを用いて、独自のRFテスト環境を構築する必要があったという。彼らは、計測機器を制御し、データを処理し、テストレポートを作成するために、「MATLAB」のスクリプトを作成/活用した。
例えば、ループバックテストにおいて、テスト装置はDUTに対し、指定された変調信号で2.405GHzのトーンを生成するよう命じる。テスト装置は、送信RF電力(ピークと平均)など、最大20個のパラメータを測定する。感度やビットエラー率などのレシーバテストも実施する。
テスト装置メーカーがBluetoothに対応したRF IC用テスト装置を開発するようになると、CSR社はそれらを使用するようになった。現在、同社のエンジニアは、Rohde & Schwarz社、Agilent社、およびアンリツのBluetoothテスト装置を使用している。CSR社が3社の計測機器を所有していることには意味がある。エンジニアは、顧客のテストの状況を再現する必要があるため、顧客と同じテスト装置を所有しているのは重要なことなのである。
CSR社のエンジニアは、すぐには専用のBluetoothテスト装置に移行しなかった。「テスト装置メーカーと協力して、各メーカーの装置用のテストプログラムを開発している。メーカーのテスト装置が第2世代、第3世代になるまで使用を待たなければならないこともあるし、それらのテスト装置を採用した後でも、一部のテストについては依然、独自のテスト環境を使用する場合がある」と同社のBlackwell氏は説明した。「専用のBluetoothテスト装置を使えば、当社独自のテスト環境よりも、一部のテストをより高速かつ正確に実行できるかもしれない。しかし、当社のエンジニアは、専用テスト装置よりも独自のテスト環境のほうが適切にテストを実行できると感じる部分に対しては、独自のテスト環境を使用する」と同氏は述べた。
脚注:
※1…Rowe, Martin, "The RFIC evaluator," Test & Measurement World, March 2009, p.9
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.