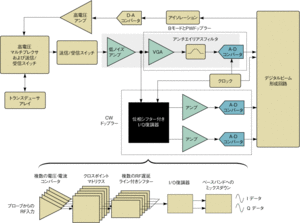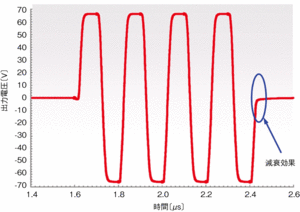医療用超音波装置のアナログフロントエンド(2/3 ページ)
超音波を利用した診断は、がんの化学療法や胎児の診断など、さまざまな医療分野で使われている。最近では手のひらサイズの持ち運び可能な超音波診断装置なども世に出てきた。進化を遂げている超音波装置であるが、その設計には検討が必要となる多種多様な項目が存在する。本稿では、最新の超音波診断装置で用いられる技術を紹介するとともに、特にその複雑なアナログフロントエンドに注目して詳細に解説を行う。
アナログフロントエンドの詳細
超音波診断装置は、信号パスにおけるデータ速度が非常に高速なマルチチャンネルの送受信システムである。ここからは、この送受信システムのアナログフロントエンドの設計について、少し深く掘り下げてみよう。
医療用途向けの超音波診断装置の信号パスは、フェーズドアレイ(位相配列)レーダーに実装されているものに似ている(図1)。ただし、超音波信号パスのほうがかなり低い励起周波数で動作する点が異なる。レーダーの受信機とは異なり、最新の超音波装置はポータブルタイプのものが多く、電池で駆動することができる(写真2)。このような装置は、2MHz〜17MHzの超音波周波数を受診者の体内へと送信する。ちなみに、周波数が低いほど、体内の奥まで観測することができる。体内での超音波信号の往復減衰量は1.4dB/cm-MHz。
ドップラー方式のシステムは、励起周波数の波長よりも小さい粒子の動きのみを識別することができる。超音波は、肺や腸など、空気で満たされた体内の空洞の部分は通ることができない。また、医師は通常、トランスデューサを使用する個所の皮膚にジェルを塗布することになる。超音波は、臓器や血流測定からの画像情報のみを送信することができる。
図1のように、医療用の超音波診断装置は、多くの点においてほかの通信システムに類似している。複数の送信器と受信器が存在することから、MIMO(Multiple Input/Multiple Output)ベースのワイヤレスシステムに似ていると言えるかもしれない。実際、ファブレス半導体企業である米Samplify Systems社のマーケティング担当バイスプレジデントを務めるAllan Evans氏は、「両者には同じA-Dコンバータを使用できるかもしれない」と述べている。
送信部は、ソナーシステムやレーダーシステムと同じようにパルスを送信する。受信部(入力部)は、音速で動作するか光速で動作するかの違いがあるだけで、レーダー受信機と同じようなものである。また、CWドップラー超音波システムの入力パスには、携帯電話の基地局や端末の設計者になじみの深いI(同相成分)/Q(直交成分)復調機能が存在している。
超音波の送信側では、高電圧パルスをトランスデューサ素子に送らなければならない。超音波診断装置は、線形トランスデューサの中央でパルスを遅延させて、音波が体内のポイントへと収束するようにする。このため、各チャンネルには専用のパルサーと、おそらくはD-Aコンバータが必要になる。電圧は通常70V以上で、ピーク出力電流は±2Aに達する。周波数範囲は2MHz〜17MHzで、バースト時間は1μsから長くて数μsである。波形は通常、単純なデジタルパルスだが、高度な装置ではD-Aコンバータを搭載してパルスの形状を調整する。この場合、送信側のドライバチップとしては、単純なMOSFETアレイではなく、高電圧アンプを用いる。D-Aコンバータが生成するこれらのパルスは、化学治療や、造影剤を使用する場合の超音波診断などにおいて有効である。バースト波形の品質は、画質にも影響を与える。例えば、米Texas Instruments社は、同社のパルサーIC「TX734」において、バースト終了時に過度なリンギングが生じないように設計している(図2)。CWドップラー方式の装置では、トランスデューサアレイの半分を送信器として、残りの半分を受信器として使用する。
150Vの送信パルスは、通常のアンプシステムにとっては過負荷である。そのため、初段のブロックではスイッチによって送信パルスからアンプを保護し、トランスデューサ内で高速に切り替えを行って音波エコーを受信できるようにする。これらのスイッチは、16個のアナログチャンネルから64素子のトランスデューサへと多重化するシステムとは切り離されている。通常、超音波システムには、信号パスの過負荷を防ぐための受信器スイッチが用いられている。そのスイッチは、サンプリングオシロスコープのフロントエンドと同様に、電流型ダイオードブリッジである場合が多い*2)。
ゲインブロックの初段には、固定ゲインの低ノイズアンプが配置される。通常20dBほどの増幅度とし、ノイズを最小化するためのアクティブ終端回路を持つ場合が多い。このアンプのノイズにより、信号パス全体のS/N比が制限される。また、同アンプは、信号がクリップしないように十分なダイナミックレンジ(電源電圧)を必要とする。トランスデューサの最も近くにある受診者の体内の骨など、固い物の表面から反射した場合、入力信号は0.5Vppにもなり得る。さらに、入力が過負荷になった場合にも、同アンプが直ちに飽和状態から抜け出せるようになっていなければならない。
メーカーは低ノイズアンプの製造プロセスとして、SiGe(シリコンゲルマニウム)プロセスまたはCMOSプロセスをよく用いる。これらのうち、SiGeプロセスのほうが線形性が高く、雑音指数が低い*3)。SiGeプロセスを採用したアンプは、より高い電源電圧で動作させることができ、アンプが過負荷にならないようにすることができる。SiGeのもう1つの利点は、フリッカノイズが低いことである。これはCWドップラー方式では、重要な基準となる。フリッカノイズの影響により、受信器スペクトラムにおいてすそが広がり、スカートのような形状になる。この位相ノイズは、小さなドップラー信号を消してしまうため、血流の遅くて小さな変化が表示できなくなる。
一方、大きなCMOSトランジスタを使用すると、電圧ノイズが小さくなる。例えば米Analog Devices社は、「当社の低ノイズアンプ『AD9272』の終端ノイズレベルは、どのようなアナログフロントエンドよりも低い」と主張している。CMOSは、基本的に入力バイアス電流が流れず、電流ノイズ仕様に優れている。Analog Devices社で「AD927x」ファミリの製品ライン担当プロジェクトリーダーを務めるCorey Peterson氏は、「CMOSは、入力ノイズ電流が非常に少ないという利点がある。超音波プローブのインピーダンスが高い場合には、入力ノイズ電流が入力ノイズ電圧と同様に重要になる」と述べる。同氏は、同社のトリプルウェルプロセスが、デジタル基板電流によるアナログ信号への干渉を防止すること、また、大きな入力トランジスタを使用することによりフリッカノイズを許容レベルにまで低減することができることも指摘している。CMOSではフリッカノイズのコーナーがどうしても高くなるが、CWモードを使用しないケース、または装置が低性能のポータブル品である場合は、許容できることが多い。
低ノイズアンプを通過すると、信号は従来型のBモード/PWドップラーパスと、CWドップラーパスに分かれる。従来型パスには、VGA(可変ゲインアンプまたはPGA(プログラマブルゲインアンプ)があり、通常40dBほどのゲインで増幅する。VGAのゲインは、各パルスを受信するごとに動的に変動し、体内の奥深くから反射した信号に対してはさらにゲインを増加させる。この手法により、チャンネルのS/N比を110dB程度確保でき、12ビットA-Dコンバータの実効ダイナミックレンジ70dBを超える。低ノイズアンプと同様に、VGAの帯域幅は約20MHzである。VGAの最大の特徴は、過負荷が生じた場合に早く回復させられることである。固い組織や骨により大きな信号が反射すると、VGAが過負荷になることが考えられる。過負荷が起こると、ドップラーシステムでは血流と識別できない周波数変調が生じる可能性がある。システムは、この信号を検知して受信時にゲインを低下するが、VGAが早く過負荷から回復すれば、それだけシステムも処理のために必要な情報を早い段階で得ることができる。
アンプとA-Dコンバータのベンダーは、過負荷からの回復特性の測定をそれぞれ異なる方法で行っている。この測定は1つの仕様に即したものではなく、システムに生じる過負荷の確率的な性質に依存する。Analog Devices社の医療部門マーケティングマネジャを務めるScott Pavlik氏は、「顧客と慎重かつ密接に作業し、システムで生じる過負荷の状態を考慮して部品の仕様に反映させる必要がある」と述べている。
VGAの後段には、アンチエイリアスフィルタとしてSAW(Surface Acoustic Wave:表面弾性波)フィルタなどのパッシブフィルタが続く。アンチエイリアスフィルタのロールオフ特性と平坦性が、高い周波数領域の高調波成分と主信号が混ざって信号品質が低下するのを防ぐのに十分となるよう、A-Dコンバータは一般的に50メガサンプル/秒(MSPS)程度の変換速度で動作させる。アクティブフィルタを使う場合、過負荷からの回復も高速化しなければならないが、パッシブフィルタには回復期間は必要ない。SAWフィルタの過負荷特性も評価する必要があるが、それらは過負荷からほとんど瞬時に回復するはずだ。
信号は、最後にA-Dコンバータに到達する。上述したとおり、A-Dコンバータとしては通常、12ビット/50MSPSクラスのパイプライン型のものが用いられる。古いシステムではBモードの走査に8ビットクラスのA-Dコンバータを使用していたが、パルス波を使用するドップラー方式では12ビットの分解能が必要となる。検討すべきもう1つの要素は、高調波画像処理モードである。超音波パルスによって圧迫された組織は、2次高調波を反射する。12ビットA-Dコンバータでは、この高調波を検知し、システムは組織の圧迫レベルを補正することにより、走査の分解能を上げる。SAR(逐次比較)型A-DコンバータのほうがS/N比に優れているが、パイプライン型のA-Dコンバータで十分である。信号チェーンのS/N比を左右するのは、A-DコンバータではなくVGAである。A-Dコンバータについては、過負荷からどれだけ早く回復するかのほうが、S/N比よりも重要かもしれない。
超音波システムでは、コンティニュアスタイム(連続時間)方式のΔΣ型A-Dコンバータ(以下、CTコンバータ)を使用することもできる。この構成であれば、システムの消費電力が少なくなる。CTコンバータでは、内部のループフィルタがエイリアスの発生を抑える役割を果たすので、アンチエイリアスフィルタも不要である。ただし、CTコンバータの場合、内部のループフィルタが帯域幅を制限するため、低速でのサンプリングは行えない。すなわち、50MSPSのCTコンバータであれば、25MSPSや40MSPSでは使用できない。また、過負荷に対する回復特性にも問題がある。一般にパイプライン型A-Dコンバータでは、パイプラインとは別の部分でサンプル値を保持するため、本質的に過負荷に対する回復特性に優れており、通常は1サンプルの間に回復する。一方、CTコンバータでは、内部積分器にクランピング回路を搭載することにより、過負荷に対する回復に対処する必要がある。これにより、過負荷の状態にある間のS/N比は低下し、消費電力は増加してしまう。とはいえ、通常、数サイクルで飽和状態から抜け出せるので、この消費電力の増加が深刻な問題になることはないだろう。
S/N比の仕様は紛らわしいので注意が必要である。Maxim社のScampini氏は、「ナイキスト帯域全体に対し、優れたS/N比を示すA-Dコンバータが必要だ」と述べる。同氏は、A-Dコンバータのリファレンス電源のフリッカノイズによって、搬送波付近のS/N比が低くなる場合があることも警告した。
なお、超音波診断装置では、12ビットデータが数十チャンネル分も存在する。従って、信号を受け取るのが大規模のFPGAであっても、パラレル出力では端子数が足りなくなる。そのため、この用途向けのA-Dコンバータは、LVDS(Low Voltage Differential Signaling)などのシリアル出力端子を備えている必要がある。
アナログフロントエンドのもう1つの信号パスは、CWドップラー用である。このパスのS/N比は、Bモード/PWドップラーパスの110dBよりも高い必要がある。Samplify社のEvans氏は、「送信信号は連続的であることに注意してほしい。血管の壁からの反射は、血管内を流れる血液のドップラー分散よりもずっと大きいことも想像できる。CWドップラーでは、154dBm/Hzのダイナミックレンジを維持することが求められる」と述べる。
CWドップラー方式ではパルスを使用しない。そのため、大きな信号を一定時間除去したり減衰したりすることによって無視するということが行えない。その代わりに、低ノイズアンプの後段で超音波信号を取り出し、アナログ信号処理を実行する復調部へと送ることができる。ドップラー信号では位相が変化するため、高度な通信技術で使用されるI/Q復調を、2MHzのCW信号からベースバンドにミックスダウンするために適用することが可能である。次にI/Q成分は、高分解能、低速サンプリングのA-Dコンバータへと送られる。ここで用いるA-Dコンバータとしては、16ビット/18ビットで150キロサンプル/秒または100キロサンプル/秒クラスのものが適切である。その後の復調処理により、信号の周波数は送信パルスの周波数から血管内の血流に対応する周波数へと下げられている。その後、I/Q成分はビーム形成用の処理を担うFPGAのスペクトル処理サブセクションへと送られる。
脚注:
※2…"Sampling Notes," Tektronix, 1964
※3…『SiGeが切り開く半導体の未来』 (Paul Rako、EDN Japan 2009年7月号、p.38)
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.