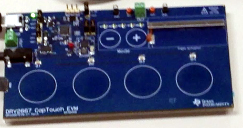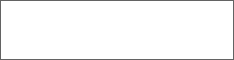圧電素子(ピエゾ素子)
圧電素子とは、圧電効果を備えた物質、すなわち圧電体を利用した電子デバイスのこと。圧電効果とは、物質に圧力を与えると電圧が発生する、もしくは電圧を印加すると物質自体が変形する現象である。英語では、圧電素子を「piezoelectric device」と呼ぶ。このため日本国内でも、ピエゾ素子と呼ばれることが多い。
圧電素子の具体例としては、振動子やスピーカー、ブザー、アクチュエータ、モーター、センサ、フィルタなどがある。いずれも、多くの電子機器に採用されており、エレクトロニクス業界において欠かすことができない存在になっている。
代表的な存在は水晶
圧電体の中で代表的な存在なのが水晶である。かつては、鉱山から産出された自然水晶を使っていたが、1960年代から人工水晶の本格的な量産が始まり、現在では水晶デバイスのほとんどが人工水晶を使っている。
水晶デバイスには、水晶振動子や水晶発振器、水晶フィルタなどがある。例えば、水晶振動子では、電圧を印加するとある一定の周波数で振動することを利用して、時計の基準信号やマイコンなどのクロック信号源などで活用されている。
スピーカーやブザー、アクチュエータ、モーターなどの圧電素子で利用されている圧電体は、セラミックス材料が多い。具体的には、チタン酸バリウム(BaTiO3)や、チタン酸ジルコン酸鉛(いわゆるPZT)、酸化亜鉛(ZnO)などだ。例えば、圧電スピーカーでは、電圧をかけた結果として発生する圧電体の振動で空気を振るわせて音圧を得る仕組みである。ただし、1層の圧電体では大きな音圧が得られない。そこで、積層セラミック・コンデンサ(MLCC:multi layer ceramic capacitor)で使われている、薄いセラミックス・シートを積み重ねる技術を応用し、振動を拡大して大きな音圧を得ている。
このほか、弾性表面波(SAW:surface acoustic filter)では、水晶材料のほか、ニオブ酸リチウム(LiNbO3)やタンタル酸リチウム(LiTaO3)などが使われている。
駆動には、高電圧の印加が必要
圧電体は、一般に誘電率の高い絶縁体である。従って、この圧電体を利用したアクチュエータなどを駆動する際には、100Vを超える高い電圧を印加する必要がある。多くの場合、専用のドライバICが不可欠だ。
例えば、米テキサス・インスツルメンツ(TI)社では、タッチパネルに搭載するハプティクス(触感フィードバック)機能に向けて、圧電(ピエゾ)素子駆動用ドライバIC「DRV8662」を製品化している。このICは、昇圧型DC-DCコンバータ回路を内蔵しており、40Vpp〜200Vppの電圧を圧電素子に印加できる。ドライバ回路全体の実装面積は52.2mm2(9mm×5.8mm)と小さい。
競合他社品は、昇圧型DC-DCコンバータ回路を内蔵しておらず、トランスやMOSFETを外付けしてフライバック・コンバータ回路を組む必要があった。このため、ドライバ回路全体の実装面積は120mm2(10mm×12mm)に達してしまう。従って、同社のドライバICを使えば、実装面積を約50%削減できるわけだ。
提供:日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
アイティメディア営業企画/制作:EDN Japan 編集部/掲載内容有効期限:2013年3月31日
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.