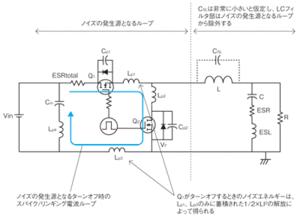DC-DCコンバータのノイズ対策[理論編]:徹底研究!ノイズの発生原因を理解する(2/5 ページ)
加害者か、被害者か
ノイズの分類方法としては、もう1つ、学術的なものではなく、実務的なものがある。
スイッチング方式のDC-DCコンバータに関しては、それを搭載する機器側の技術者から「ノイズの問題」という言葉を聞くことがある。その場合、観測場所によってノイズを分類していることが多い。その観測場所は、ほぼ以下に示す4つに集約される。
■入力端子
DC-DCコンバータの入力端子に現われる高周波ノイズは、スイッチング時のパワーMOSFETのターンオフに伴って発生するスパイク/リンギング電流と、入力コンデンサのESL(等価直列インダクタンス)によって引き起こされるものだ。ESLをL、流れる電流をiとすると、発生するノイズの電圧はL×di/dtで表される。このノイズが現われる入力端子は、被害者的な要素を持っていると言える。
■出力端子
出力端子のノイズは、スイッチノードのスパイク/リンギング電圧がインダクタや基板の寄生容量を経由して伝わり、出力リップル電圧に重畳することで現われる。これも被害者であろう。
なお、入力端子にも出力端子にも、スイッチング周波数の基本波成分とスパイク/リンギングによる数百MHzの高周波ノイズ成分の両方が現われる。ただし、基本波成分については、そのリップルがよほど大きくない限り、大きな影響を及ぼすことはあまりない。影響を及ぼすのは、数百MHzの高周波ノイズである。特に、入力端子ノイズは、共通の入力バスを介してほかの電源回路や回路パターンに伝わるので影響が大きい。
■放射
放射ノイズは電源から空中を通って基板のレイアウトパターンなどに現われる。必ずしも特定の位置に現われるわけではないので、入力端子/出力端子の分類とは少し性質が異なる。
近傍界(電磁界の波長をλとした場合に、距離がλ/2π以下)では、機器の基板パターンなどにループが存在すると、電磁誘導によって式(2)で表されるノイズが発生する。一方、遠方界のノイズは、ストリップ線路に電波として現われる。
■スイッチノード
スイッチノードのノイズは、パワーMOSFETであるQ1、Q2のターンオフ時にスパイク/リンギング電圧の波形として観測される。実は、このときスパイク/リンギング電流が流れており、それが1次側の高周波リンギングループに流れ、そのループに存在する寄生インダクタンスによってL×di/dtのスパイク/リンギング電圧が発生する。これが入力コンデンサの端子にノイズを引き起こしたり、スイッチノードのノイズを引き起こしたり、インダクタや基板の寄生容量を介して出力端子やほかの機器に伝わったりする。
このQ1、Q2のターンオフ時に発生するスパイク/リンギングこそが、高周波の電流/電圧ノイズの発生源、すなわち加害者である。
ノイズを考慮した等価回路
ここまでの説明により、対策の対象となるノイズが、パワーMOSFETのターンオフ時に発生するスパイク/リンギングノイズであることが理解できたはずだ。その影響を抑えるには、まずこの高周波ノイズが発生するメカニズムを明確にする必要がある。その上で、そのノイズがどのように入力端子、出力端子に現れるのか、また電磁波として放射していくのかといったことを把握しなければならない。そのためには、まずノイズについて考慮した回路モデルを考える必要がある。
先述したように、降圧型コンバータの基本回路は、図1のようなものとなる。DC-DCコンバータとしての基本動作を考える上ではこれで十分だが、高周波ノイズについて検討するには素子やレイアウトに存在する寄生要素について考慮しなければならない。
スイッチング素子であるパワーMOSFETには、チップのボンディングワイヤーによる寄生インダクタンスやドレイン‐ソース間容量が存在し(ここでは話を単純化するために、MOSFETのミラー容量、ゲート容量は無視する)、入出力のコンデンサについてはESLを考慮しなければならない。また、インダクタの巻き線間にもわずかではあるが寄生容量が存在する。さらに、配線、レイアウト、ビアによっても寄生インダクタンス/寄生容量が形成される。これらの寄生要素を考慮すると、図3のような等価回路が得られる。
先述したように、ここではノイズの発生源(加害者)と、ノイズが伝搬して観測されるところ(被害者)を切り分けて考えるために、図3のインダクタLの巻き線間の寄生容量、および基板パターンの寄生容量CSLは非常に小さい(数pF以下)と仮定する。すなわち、ノイズの発生に関与しているのは、入力トランジスタCin、ハイサイドMOSFETのQ1、ローサイドMOSFETのQ2で構成される高周波リンギングループに存在する寄生要素のみであるとする。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
記事ランキング