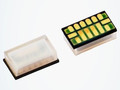電源設計
DC/DCコンバータをはじめLDOレギュレータ、IGBT、ダイオードなどパワーデバイス関連の話題をEDN Japan/EE Times Japanから集めています。電源設計に役立つ情報を随時、更新していきます。
【PR】Sponsor’s Special Contents
「インダクタの選択」の手間も減らし開発を効率化
AI(人工知能)やEV(電気自動車)などの普及で電力消費量が増加し、電源供給システムはより省スペースでより大電力を供給する電力密度の向上が求められている。Texas Instruments(TI)が発表したパワーモジュールは、磁気部品と電源チップをワンパッケージに集積する新しい技術「MagPack」を用いることで電力密度を2倍に高めた。
「小さくても大電力が欲しい」に応える
太陽光発電システムやデータセンター、EV(電気自動車)など、さまざまなアプリケーションの電源ユニットにおいてより高い電力密度の要求が高まっている。Texas Instruments(TI)が発表した100V GaN統合型パワーステージとトランス内蔵の1.5W絶縁型DC/DCモジュールは、このニーズに応える製品だ。100V GaN統合型パワーステージはシリコンを採用する場合に対してボードサイズを40%削減できる。トランス内蔵の1.5W絶縁型DC/DCモジュールでは外付けの大型トランスが不要なのでソリューションサイズを最大で約80%削減可能だ。
シャント抵抗不要で高効率化と小型化を両立
ノートPCなどの電源アダプターは「大きくて重いもの」。そんな“常識”が変わるかもしれない。Texas Instruments(TI)が発表した新しいGaN FETは、電流センシング機能を統合したことでAC/DC電力変換システムの高効率化と小型化を両立させられる製品だ。標準的な67W電源アダプターであれば、Si FETを用いた従来品よりも50%小型化できる。電源アダプターやUSB電源の大幅な小型化に大いに貢献するはずだ。
システムの高効率化を支える電流センサー
電気自動車(EV)や工場の自動化で使われる制御機器では、エネルギー効率の向上のためにより高精度な電流センシングのニーズが高まっている。Texas Instruments(TI)はこうした要求に応えるべく、電流センシングソリューションを拡充している。2023年8月には、EVの800Vバッテリーシステムでも使えるホール効果電流センサーや電流センシングソリューションを大幅に小型化するシャント抵抗内蔵電流モニターを発表した。いずれも、電流検知システムの設計を簡素化できる製品だ。
EVの航続距離を年間で1600km延長
電気自動車(EV)において、トラクション・インバータの高効率化はEVの航続距離の延長に直結する重要な要素だ。既存のトラクション・インバータにおいてさらなる高効率化が課題となる中、Texas Instrumentsは新たなゲート・ドライバを開発した。ゲート駆動能力をリアルタイムに切り替えることでSiC-MOSFETのスイッチング損失を抑え、システム効率を最大2%向上させる。これにより、EVの航続距離を年間で最大1600km延長できる。
厳格なEMI要件の適合も容易に
自動車や産業機器などの電気システムでは、EMI(電磁干渉)対策が重要性を増している。Texas Instruments(TI)が開発したスタンドアロンのアクティブEMIフィルタICを使えば、設計や実装が難しかったアクティブEMIフィルタを容易に構成できる。従来の受動EMIフィルタよりも大幅な小型化も可能だ。
今こそフォトカプラーからの置き換えを
産業機器や医療機器において、安全性を実現するための絶縁技術は欠かせない。使用年数が数十年に及ぶことも多いこれらの機器では、絶縁性能も、同様に長い期間維持することが求められる。そうした中、寿命(経年劣化)が存在するフォトカプラーに代わる絶縁素子として注目されているのがデジタルアイソレータだ。Texas Instruments(TI)は、20年以上にわたる研究開発と自社製造の強みを生かし、最新のデジタルアイソレータをはじめとする幅広い絶縁ソリューションを手掛けている。
EVや産業機器の高電圧化に応える
システムの安全性と堅ろう性を実現するために欠かせない絶縁技術。絶縁性を確保する部品として、従来のメカニカルリレーに代わって台頭し始めているのが、可動接点部分のないソリッドステート・リレー(SSR)だ。20年にわたり絶縁技術に投資してきたTexas Instruments(TI)が電気自動車(EV)と産業機器向けに発表した新しいSSRは、従来のリレーから置き換えることで、システムの信頼性を向上しつつ、ソリューションサイズを最大90%削減することも可能になる。
電池寿命を最大20%延ばす
世界的に「省エネ」への要求が高まる中、IoT(モノのインターネット)機器を含むバッテリー駆動機器にも、さらなる低消費電力化が求められている。Texas Instruments(TI)が、低静止電流技術と統合技術を駆使して開発した新しい昇降圧コンバータは、あらゆるバッテリー駆動システムに大きな省エネ効果をもたらす。
分散型電源アーキテクチャの構成が容易に
電気自動車(EV)の電源アーキテクチャでは、小型化や信頼性向上のために、各ゲートドライバに個別のバイアス電源を割り当てる分散型電源アーキテクチャへの関心が高まっている。Texas Instruments(TI)の絶縁型DC/DCバイアス電源モジュール「UCC14240-Q1」は、トランスと閉ループ制御を統合することで小型化を実現し、分散型電源アーキテクチャに活用しやすくなっている。
汎用性はそのままに、処理性能は従来比で10倍
リアルタイム制御や産業用ネットワークのサポート、高性能処理、セキュリティなど、スマート工場や自動運転に必要とされる性能を、1チップで実現するマイコンが登場した。Texas Instrumentsは、マイコン設計のシンプルさとプロセッサレベルの処理性能を併せ持つ「Sitara AM2x」によって、マイコンの性能を“再定義”する。
どうする? ノイズ対策
今や、電子機器において不可欠となっているEMI対策。Texas Instruments(TI)は長年、EMIの低減とEMI規格適合への迅速化を実現する電源ICの開発に注力してきた。TIの最新の電源ICに搭載された、低EMI化に向けた2つのアプローチを探る。
継続的に半導体製品を確実、スピーディに届けるためのTIの取り組み
テキサス・インスツルメンツ(Texas Instruments/以下、TI)は、豊富な品ぞろえを誇る半導体製品群を確実に届け、自然災害など不測の事態が発生した場合にも半導体製品を継続して迅速に供給できるよう、さまざまな取り組みを進めている。その一環として、2021年2月にはオンライン購入サイトを刷新。高信頼性製品、最新製品をどこよりも安く、早く、簡単、確実に手に入れることができるようになった。
EVのバッテリ管理は大きく変わる
電気自動車やハイブリッド自動車で注目度が高まっているワイヤレスBMS(Battery Management System)。Texas Instruments(TI)は、同社が強みとする高精度な電源制御技術とワイヤレスマイコンを組み合わせた、最新のワイヤレスBMSソリューションを発表した。TÜV SÜDの安全性評価に準拠した、ASIL-Dのシステムを「業界として初めて」(TI)実現した。
EV用充電回路のサイズは半分に
10年間、GaNパワーデバイスの研究開発に投資し、性能と信頼性を向上してきたTexas Instruments(TI)。同社が開発した新しい650Vおよび600VのGaN FETは、Siliconドライバや保護回路を統合することで、電力密度をさらに高めた製品となっている。
不断の研究開発が支える
電源において、常に最も重要な課題の一つとなっているのが電力密度だ。電力密度の向上は、電源サイズの縮小、部品点数の減少、システムコストの削減など、多くのメリットに直結している。Texas Insrtuments(TI)は、4つの主要分野において、電力密度の向上におけるイノベーションをけん引している。
かつてない電力需要増に応える
IoTとAIの時代が到来し、さまざまな機器で膨大な量のデータが処理され、グローバルなレベルでデータが行き交うことから、増加する電力需要に応えられる拡張機能を備えたパワーエレクトロニクス製品が求められている。Texas Instruments(TI)は、こうした要件を満たす、高い電力密度や変換効率を実現した最新のGaN製品や降圧型DC/DCコンバータを展開している。
最新! 電源関連ニュース
新電元工業 D10FR60K、D2CE80K:
新電元工業は、小型化、高耐圧に対応するファストリカバリーダイオード「Kシリーズ」のラインアップを拡充した。民生家電の臨界動作PFC用途向けおよび車載インバーター向けの製品を発売する。
ローム RLD8BQAB3:
ロームは、1kW級の出力が可能な赤外レーザーダイオード「RLD8BQAB3」を開発した。発光面に採用したクリアガラスのガラスキャップにより光散乱を抑えるため、高品質なビームを得られる。
東芝 TB9103FTG:
東芝デバイス&ストレージは、車載向けブラシ付きDCモーター用ゲートドライバー「TB9103FTG」のエンジニアリングサンプルを提供する。回転速度制御不要のブラシ付きDCモーター用ゲートドライバーに必要な機能と性能に特化し、小型化した。
サンケン電気 SIM2-202B:
サンケン電気は、20A出力対応高圧3相モータードライバー「SIM2-202B」の量産開始を発表した。コンパクトながら放熱性能に優れ、高精度のサーマルシャットダウン機能や温度モニター機能などを備える。
サンケン電気 SSC4S911:
サンケン電気は、臨界モードPFC内蔵LLC電流共振電源用コントロールIC「SSC4S911」の量産を開始する。SSOP24パッケージに臨界モードのPFC制御とLLCタイプの電流共振制御を内蔵している。
日清紡マイクロデバイス NA2100:
日清紡マイクロデバイスは、産業機器向け汎用低消費電力の電圧周波数コンバーター「NA2100」を発売した。シンプルな回路構成で12ビット以上の変換精度を提供する。
新電元工業 MG074:
新電元工業は、民生および産業機器向けSiC(炭化ケイ素)パワーモジュール「MG074」のサンプル出荷を開始した。配線長が等しくなるよう内部構造を左右対称のレイアウトとし、電流経路で発生するサージ電圧の差を最小限に抑えた。
ビシェイ VS-3C05ET12T-M3など16種:
ビシェイ・インターテクノロジーは、同社第3世代品となる1200VのSiC(炭化ケイ素)ショットキーダイオード16種を発表した。埋め込み型のMPS構造を採用し、定格電流5〜40Aを用意する。
STマイクロ VNF9Q20F:
STマイクロエレクトロニクスは、車載向け4チャネルのハイサイドスイッチ「VNF9Q20F」を発表した。独自のデジタル出力電流センス機能とSTi2Fuse技術を集積した。
ソフトウェアモジュールも提供:
マイクロチップ・テクノロジーは、車載充電モジュール向けのソリューションを発表した。デジタルシグナルコントローラー「dsPIC33C」、絶縁型SiC(炭化ケイ素)ゲートドライバ「MCP14C1」、D2PAK-7L XLパッケージを採用した「mSiC MOSFET」が含まれる。
過充電検出精度は±12mV:
日清紡マイクロデバイスは、1セルリチウムイオン電池向け温度保護機能付きハイサイド保護IC「NB7120」シリーズを発売する。過充電検出精度および充放電過電流検出精度を高めた。
ツェナー電圧5.6〜36.0Vまで対応:
東芝デバイス&ストレージ(東芝D&S)は、サージ保護用ツェナーダイオードシリーズ(5種)に、各10種のツェナー電圧ランクを追加した。マイクロ秒からミリ秒オーダーの長いパルス幅のサージから保護する。
3.3〜28Vの9種の出力を提供:
マイクロチップ・テクノロジーは、宇宙グレードの耐放射線絶縁型50W DC-DCパワーコンバーター「LE50-28」ファミリーを発表した。シングル出力、トリプル出力を備える3.3〜28Vまでの9種を提供する。
静止時電流は無負荷時で2μA:
STマイクロエレクトロニクスは、車載および産業向け低ドロップアウト(LDO)レギュレーター「LDH40」「LDQ40」を発表した。3.3〜40Vの広い入力電圧に対応し、低静止電流を特徴としている。
高い信頼性を実現:
ビシェイ・インターテクノロジーは、「FRED Pt 500 A Ultrafastソフトリカバリーダイオード」モジュールの「VS-VSUD505CW60」「VS-VSUD510CW60」を発表した。前世代品よりも信頼性、耐久性が向上している。
逆回復電荷量は最大89%低減:
インフィニオン テクノロジーズは、200V耐圧のMOSFET「OptiMOS 6」ファミリーを発表した。同社前世代品と比較してオン抵抗が42%、逆回復電荷量が最大89%低減し、ソフトリカバリー特性が向上している。
- 定格電流40Aのブリッジダイオード (2022年12月28日)
- 1コンバーターのLED照明用制御IC (2022年12月19日)
- 高電圧直流入力対応のDC-DCコンバーター (2022年12月16日)
- ワイヤ保護機能付きハイサイドゲートドライバー (2022年10月4日)
- 伝導損失とスイッチング損失を軽減、小型パッケージのダイオード (2022年9月30日)
- 車載機器向け接続検知機能付き高耐圧LDO (2022年9月21日)
- 過電流保護機能搭載ゲートドライバーカプラー (2022年9月16日)
- 2セルリチウムイオン電池向け保護IC (2022年9月14日)
- ADAS向け車載LDOレギュレーター (2022年9月13日)
- +175℃動作で低伝導損失の超高速ダイオード (2022年9月12日)
- 出力定格40VのステッピングモータードライバーIC (2022年9月7日)
- バッテリーパック認証用ICなど、電池向け製品を展示 (2022年9月6日)
- SiCパワーMOSFET内蔵パワーモジュール、STが発表 (2022年9月13日)
- スナップイン型パワーアルミコンデンサー (2022年9月1日)
- 搭載用途が増える2セルリチウムイオン電池向け保護IC (2022年9月1日)
電源設計関連【入門】記事
たった2つの式で始めるDC/DCコンバーターの設計(8):
今回からステップアップ形DC/DCコンバーターについて説明していきます。まずは、ステップアップコンバーターの基本回路と動作原理について解説します。
たった2つの式で始めるDC/DCコンバーターの設計(7):
今回はDC/DCコンバーターを設計する上で欠かせない「過電流保護回路」について説明します。
たった2つの式で始めるDC/DCコンバーターの設計(6):
今回はいままで前提にしてきたチョークの電流連続性が途切れた場合のコンバーターの振る舞いについて図式を基に検討します。
たった2つの式で始めるDC/DCコンバーターの設計(1):
今回から電源設計の超初心者向けにDC/DCコンバーターの設計を説明していきます。この連載で主として使用する式はインダクタンスに関する式および、キャパシタンスに関する2つの式だけです。2つの式から導かれるインダクタンスとキャパシタンスの電気的性質を使って入門書などに記載されている基本的なコンバーターの設計をどこまで説明できるかを考えていきます。
研究者はいかにして障壁を超えてきたか:
パワーエレクトロニクス市場での存在感を高めているGaNデバイスだが、少し前まで、極めて不完全な結晶だからという理由で、半導体としては使い物にならないと見なされていた。科学者とエンジニアたちはどのようにしてその壁を乗り越えたのか。本稿ではGaNテクノロジーの起源を紹介する。
DC-DCコンバーター活用講座(1) 電力安定化(1):
DC-DCコンバーターをより深く理解するために、DC-DC回路とトポロジーについて解説する本連載。DC-DCコンバーターを使いこなすための実用的ヒントを要所要所にちりばめました。まずは、電力安定化について、トポロジーごとに解説していきます。
Wired, Weird:
今回は、“電源修理のコツ”を紹介したい。電源は「電解コンデンサーを全て交換すれば、修理できる」という極端な話もあるが、効率よく確実に電源を修理するためのポイントを実例を挙げながら説明していこう。【訂正あり】
覚えておきたい「電源測定」のきほん手順(1):
電源設計に求められる要件は、多くなっています。高効率/高電力密度、迅速な市場投入、規格への対応、コストダウンなどを考慮せざるを得ず、電源設計におけるテスト要件も複雑化しています。そこで、本連載では、3回にわたって、複雑な電源設計プロセスの概要と、プロセスごとのテスト要件について説明していきます。
- 交流を直流に変換する「AC-DC電源」のきほん (2015年3月26日)
- デジタル電源再入門 (2013年7月1日)
- 電源サブシステム入門 (2007年3月1日)
- パワー半導体の基礎知識 (2013年7月16日)
- コンセントからの電気が電子機器に伝わるまで (2012年6月15日)
- いまさらだけど電気・電源についておさらいしよう (2012年6月13日)
電源設計テクニック!
初めて使うデジタルマルチメーター(3):
デジタルマルチメーターの基礎的な使い方について解説する本連載。今回は直流/交流の電流測定および周波数測定と仕様の見方について説明する。
Wired, Weird:
スイッチング電源が普及してしばらくがたつ。PFC回路の搭載など進化してきた一方で、弱点を抱えているのも事実で、焼損の可能性を持つスイッチング電源は少なくない。スイッチング電源、PFC電源の弱点をいま一度見つめ、安全性を高める方法を考えてみたい。
2つの大きな課題とは?:
今回は、正電圧出力に比べてそれほど一般的ではない負電圧出力(または反転)DC-DCコンバーターソリューションの基本を解説します。
Wired, Weird:
今回は電源投入の約5秒後にブレーカーから火花が出て電源が落ちる高圧電源の修理の続きだ。
SiC採用のための電源回路シミュレーション(3):
SiCパワーMOSFETを採用した電源回路の回路シミュレーションを実行する際は、設計したプリント基板の配線レイアウトを解析し、その寄生インダクタンスや寄生キャパシタンスを分布定数として高精度で抽出する必要がある。
SiC採用のための電源回路シミュレーション(2):
SiCパワーMOSFETのデバイスモデルの精度向上には、「大電流/高電圧領域のId-Vd特性」および「オン抵抗の温度依存性」を考慮しデバイスモデルに反映させることも重要となる。今回はこの2点に関する解説を行う。
ロームのQuiCur(クイッカー):
ロームは、電源ICの負荷応答特性を向上させる新たな電源技術「QuiCur(クイッカー)」を確立したと発表した。電源回路の設計工数を大幅に削減することが可能になる。
SiC採用のための電源回路シミュレーション(1):
スイッチング動作が極めて高速なSiCパワーMOSFETを用いた電源回路設計では、回路シミュレーションの必要性に迫られることになるが、従来のモデリング手法を用いたデバイスモデルでは精度面で課題があった。本連載では、この課題解決に向けた技術や手法について紹介する。
DC-DCコンバーター活用講座(47):
電磁気学入門講座。今回は「相互インダクタンス損失」と「渦電流損失」について説明していきます。
Wired, Weird:
取引先から紹介された会社からモータードライバーの修理を依頼された。不具合の症状は『高速回転は問題なく動作するが、低速回転で逆回転する。低速の正常回転数 0.66に対し現在は0.05』と非常に具体的だった。この症状からするとモーターのトルクが足りてないようだ。依頼者は現場で活躍している人なので、何とか依頼に応えたいと思い修理を引き受けた。
DC-DCコンバーター活用講座(46):
今回は、コアの飽和を制御する方法として、コアにエアギャップを設ける「エアギャップインダクター」や、標準的な「コア形状」について解説します。
電源IC活用術:
ユーザー・プログラマブルPMICならば、同じPMICを複数のプロジェクトで再利用できるため、迅速にプロトタイプ作成が進み、開発期間を短縮できます。
電源設計のヒント:
高周波数のスイッチングでも、フライバックトポロジを最適化して効率をはるかに高められる新しい方法があります。この記事では、ゼロ電圧スイッチング(ZVS)が可能なアクティブクランプフライバックトポロジで電力密度を高められる仕組みを説明し、さらなる効率向上のためにトポロジを最適化する2通りの方法を紹介しようと思います。その1つはスイッチノード容量の削減、もう1つは2次共振回路の利用です。
Q&Aで学ぶマイコン講座(56):
マイコンユーザーのさまざまな疑問に対し、マイコンメーカーのエンジニアがお答えしていく本連載。56回目は、初級者の方からよく質問される「マイコンの電源の逆電圧が端子に印加されたら何が起こる?」についてです。
WBGパワー半導体を使う:
年々注目度が増すワイドバンドギャップ(WBG)半導体。その中で、現在最もシェアが高いのはSiC(炭化ケイ素)だ。SiCスイッチの特性と、同素子を使う際の設計上の注意点を説明する。
- セラミックキャパシター(3) ―― 特徴と構造、製造工程 (2020年9月28日)
- LEDの特性(3)熱に関する検討や温度ディレーティング (2020年9月17日)
- セラミックキャパシター(2) ―― 誘電体とは (2020年8月28日)
- ワインセラー用の海外製電源の修理(前編) (2020年8月7日)
- セラミックキャパシター(1) ―― 原理、歴史などその概要 (2020年7月28日)
- セラミックキャパシター(4) ―― 温度特性 (2020年10月29日)
- LEDの特性(4)輝度補正やRCDドライバを使用した回路案 (2020年10月20日)
- LEDの特性(1)定電流でLEDをドライブ (2020年6月18日)
- なぜ? 放置されてしまった低レベルな設計ミス (2020年7月7日)
- DC-DCコンバーターの信頼性(5)半導体の信頼性とESD (2020年5月28日)
- 負の出力電圧を動的に調整する「ミッシングリンク」 (2020年4月23日)
- 導電性高分子アルミ電解キャパシター(3)―― 製造工程とリーク電流発生メカニズム (2020年6月26日)
- 48V分散型電源アーキテクチャの利点とは (2020年4月8日)
- 導電性高分子アルミ電解キャパシター(2)―― 特徴と使用上の注意 (2020年5月27日)
- GaNで高効率な電源設計を、駆動方法がポイントに (2020年4月22日)
- エイブリック、車載用LDOレギュレーターICを発売 (2020年3月17日)
- 日本TI、高電力密度の絶縁型DC-DCバイアス電源 (2020年2月14日)
- DCDCコンバーターの信頼性(4)コンデンサーの信頼性 (2020年4月30日)
- 電源の電圧をマイコン内蔵A-Dコンバーターで測定する裏技 (2020年4月6日)
- DC-DCコンバーターの信頼性(3)信頼性設計とPCBレイアウトの考慮事項 (2020年3月26日)
- アルミ電解コンデンサー(8)―― 市場不良と四級塩問題 (2020年3月23日)
- DC-DCコンバーターの信頼性(2)環境ストレス要因とMTBF値の使用 (2020年2月28日)
- シンプルなのになぜ!? 短期間で故障を繰り返す電源【前編】 (2020年2月4日)
- 電源ノイズがデルタ-シグマADCに与える影響の理解 (2020年1月28日)
- ありがちな故障と思ったら…… ステッピングモータードライバーの修理【前編】 (2019年11月13日)
- 降圧回路のEMIをカンタンに低減する3つのTips (2019年10月23日)
- SiC登場で不可避な電源回路シミュレーション、成功のカギは「正確な実測」 (2019年9月11日)
- どう熱を制するか ―― 車載デュアルUSBチャージャー考察 (2019年10月9日)
- ポイントは“負電源” ―― 高性能温度調整器の修理 (2019年10月8日)
- 突然タンタルコンが燃えた ―― バッテリーを逆接した基板の修理(1) (2019年5月8日)
- MOSFETを内蔵した降圧レギュレーターで電力密度を向上 (2019年3月25日)
- フィルターレイアウトを考える (2019年3月6日)
- 代替部品が見つからない減圧ポンプコントローラの修理 (電源編) (2018年11月6日)
- 電話端子で大容量コンデンサーをトリクル充電 (2018年10月1日)
- DC/DCコンバータの周辺部品削減と安定化 (2015年11月25日)
- シーケンサの修理(1)4級アンモニウム塩との闘い (2015年11月9日)
- DC-DCコンバーターの突入電流と負荷の制限 (2018年8月6日)
- DC-DCコンバーターの絶縁と出力リップル (2018年5月21日)
- スルーレート制御で電源のEMIを減らす (2015年10月13日)
- 3万円オシロの修理【完結編】安すぎる部品に落とし穴 (2015年9月9日)
- DC-DCコンバーターの効率の計算 (2018年4月16日)
- 開ループと閉ループの設計 (2018年1月22日)
- リチウムイオン電池用リニア充電器のテスト回路 (2017年11月27日)
- カレントミラーを使って定電位差出力を得る (2017年11月6日)
- 過電圧と低電圧の監視を低コストで実現する (2017年10月16日)
- 車載電子機器の市場トレンドと求められる電源IC (2017年8月4日)
- 車載システム向けのUSB Power Deliverについて (2017年7月25日)
- 完全統合型の信号/電源アイソレーターを用いた低放射の実現 (2017年6月19日)
- データのバックアップと保持のための電源ホールドアップ (2017年6月16日)
- 自己消費300nAに抑えた昇圧レギュレーター (2017年3月14日)
- 高精度、高速応答の低電圧対応COT制御DC-DCコン (2017年2月20日)
- 漏れインダクタンスを使用したフライバックコンバーター(3) 小信号モデル化 (2017年3月16日)
- 漏れインダクタンスを使用したフライバックコンバーター(2) 平均モデル化 (2017年1月30日)
- 亡き父が残してくれたマルチ電圧出力ACアダプターの修理 (2017年1月11日)
- 漏れインダクタンスを使用したフライバックコンバーター(1)ハードウェア概要 (2016年12月15日)
- 過電圧監視がない電源の末路 (2016年8月4日)
- 電池で駆動できる低電力用途向け電子負荷 (2016年10月18日)
- MOSFETの実効容量値を簡単に求める術 (2016年9月7日)
- 電源オン時のシーケンスを設定できる回路 (2016年8月3日)
- 白物家電でのモーター駆動の新課題と対処技術 (2016年6月28日)
- マージンのない電源の危険性 (2016年6月6日)
- 電源システムハードウェアのソフトマネジメント (2016年5月31日)
- GaNに対する疑念を晴らす (2016年5月27日)
- 疑似共振型コンバーターをCMOS ICで制御する (2016年5月12日)
- スイッチノードリンギングの原因と対策 (2016年4月26日)
- 2つのICで低リップル、高効率の電源回路を実現 (2016年4月5日)
- 並列接続IGBTの駆動 (2016年3月31日)
- 不良シーケンサの修理――再び動くまでの道程 (2016年3月14日)
- ブラシレスDCモーターの利点と課題解決例 (2016年3月10日)
- 広範囲の負電圧から正電圧を得る回路 (2016年2月26日)
- 不良シーケンサの修理――配慮のない設計が招く必然の故障 (2016年2月12日)
- シーケンサの修理(2)CPU異常の原因も電解液!? (2015年12月9日)
- 並列型レギュレータで直流定電圧を生成する (2015年7月28日)
- SW電源の解析 (2015年6月29日)
- 白い雪ならぬ“白いゴミ”が積もった基板――光源機器の修理 (2015年6月10日)
- 3万円オシロの修理、高圧パルス電源は甘くない【暫定修理編】 (2015年8月5日)
- 単一電源で動くリニア・パワー・ドライバー (2015年8月4日)
- 電気2重層キャパシタで電池の出力を高める (2015年6月24日)
- IGBTの熱計算により 電力設計の有効性を最大化 (2015年6月9日)
- 保護回路付きのハイサイド・ドライバー (2015年5月18日)
- ファンに振り回された!?――ユニット電源の修理(1) (2015年1月13日)
- 整流回路の突入電流を簡単な部品で制限 (2015年2月27日)
- フィードバックがない“暴走電源” (2014年10月8日)
- FPGAに向けた電源シーケンス回路 (2014年9月24日)
- ATX電源の修理 〜1台目〜 (2013年12月16日)
- 昇圧型レギュレーターに降圧動作を追加する (2013年1月11日)
記事ランキング
- SiCパワーMOSFETのデバイスモデル、オン時の容量考慮で精度が大幅向上
- いまさら聞けないジャイロセンサー入門
- 組み込みセキュリティ規制の概要解説:EUサイバーレジリエンス法とは?
- 総帯域幅が従来比6倍のUSBペリフェラルコントローラー
- SiCパワーMOSFETを採用した電源回路、配線レイアウトの考慮が高精度解析に不可欠
- 無線送信機向けRFトランスミッターIC
- 次世代車載向けセキュリティコントローラー
- 5G基地局向け吸収型SPDTスイッチ
- SiCパワーMOSFETのスイッチング特性、大電流/高電圧領域の測定で解析精度が向上
- SiC登場で不可避な電源回路シミュレーション、成功のカギは「正確な実測」