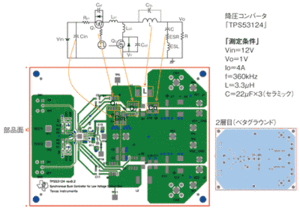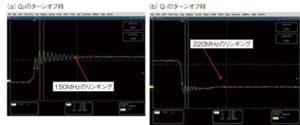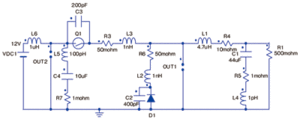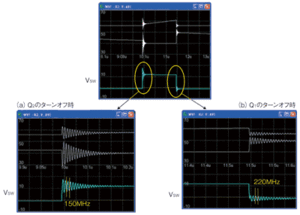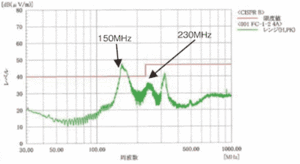DC-DCコンバータのノイズ対策[理論編]:徹底研究!ノイズの発生原因を理解する(4/5 ページ)
実測とシミュレーションによる確認
『理論編』の締めくくりとして、ここまでに説明した内容を実験とシミュレーションの結果から確認しておこう。
■実験による確認
まず、ノイズの発生源について確認するために、パワーMOSFETのターンオフ時のスイッチング電流、スイッチング電圧を再現してみる。
図8は実験に用いた回路基板のレイアウトを示したものである。入力電圧が12V、出力電圧/電流が1V/4A、スイッチング周波数が360kHzという条件で実験を行った。図9に示したのが実測した波形である。Q2のボディダイオードD1のターンオフ時に発生するリンギングの周波数は約150MHz、Q1のターンオフ時には周波数が220MHzのリンギングが観測されている。
ここで、これらの周波数の妥当性について検討してみる。まず、Cin、Q1、Q2で構成されるループの寄生インダクタンスの値が問題になるのだが、図8の基板レイアウトは理想的なものに近い。そこで、少々粗い方法だが、Q1、Q2のパッケージ(SOP8)のリードとパッケージ内のボンディングワイヤーによる寄生インダクタンスが問題になり、ボンディングワイヤー1mmを1nHとおいて、Q1とQ2それぞれの値が1nH、1nHであると仮定しよう。一方、寄生容量に関しては、共振にかかわるQ1、Q2のドレイン‐ソース間容量は、データシートを参考にしてそれぞれ200pF、400pFであると仮定する。すると、式(3)と(4)から、Q2がターンオフする際のリンギングの周波数は178MHz、Q1がターンオフする際のリンギング周波数は250MHzと計算できる。
■シミュレーションによる確認
続いて、シミュレーションによる確認結果を示す。シミュレーションには電源シミュレータとしてよく使われる「SCAT(バージョンはK.488 PR4)」(計測技術研究所)を利用した。図10はシミュレーションに用いた回路図、図11はターンオン/ターンオフ時にスイッチノードに生じるリンギング電圧の波形を示したものだ。
図11を図9と比べると、リンギングの周波数がよく一致していることがわかる。このことから、ノイズの発生メカニズムとシミュレーションに用いた寄生要素の値は妥当であると言える。
■放射ノイズの測定
最後に放射ノイズの測定結果を示しておく(図12)。これはEMI(電磁波干渉)測定サイト(3m法)における放射ノイズの測定結果である。これを見ると、150MHzと230MHz近辺にノイズのピークが確認できる。これらの周波数はQ1、Q2のターンオフ時に生じるリンギングノイズの周波数とほぼ一致している。このことから、スイッチングによって発生するノイズが放射によって伝搬していることがわかる。
なお、図12を見ると310MHzにもノイズのピークが存在している。これについては、本稿では取り上げなかったほかの寄生要素やコモンモードノイズの影響が考えられる(別掲記事『コモンモードノイズの影響』を参照されたい)。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
記事ランキング