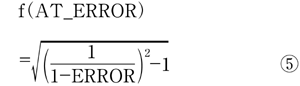非補償型オペアンプの基本を知る(1/2 ページ)
ユニティゲインでも安定に動作するよう内部補償されたオペアンプには、ユーザーにとって、より容易に安全な回路を設計できるというメリットがある。しかし、そうした「完全補償型オペアンプ」では、AC性能の主要部分を犠牲にしていることも事実だ。本稿では、この種の製品とは異なる方針で設計された「非補償型オペアンプ」の概要とそのメリットについて解説する。
オペアンプの「有効帯域幅」
例えば、センサーからの信号を処理する回路において、振幅誤差を最小限に抑えたいというのはよくあることだ。こうした考えに基づく設計では、オペアンプの閉ループゲイン誤差について、センサーの動作周波数の全域にわたって考慮しなければならない。通常、オペアンプの帯域はゲインが3dB低下する周波数(以下、−3dB周波数)で規定されるが、−3dB周波数でのゲイン誤差は約30%にもなる。
オペアンプ単体の周波数応答と、オペアンプ回路として必要な増幅度の精度を関連付けるには、「有効帯域幅」という概念を用いると便利である。この有効帯域幅は、ゲイン誤差が所望値以内である範囲を表すものとする。
センサーの応答周波数は比較的低い。こうした低周波域では、オペアンプの開ループゲインが有限であることが理由で生じるゲイン誤差は小さい。低周波域に限れば、その最大周波数が有効帯域幅に含まれているか否かは、単極(シングルポール)で閉ループの周波数応答モデルを基に簡単に計算できる。また、オペアンプのデータシートに記載されるゲイン帯域幅積(GB積:ゲインと帯域幅の積)のような規格値を基に、有効帯域幅を求めるのも有効な方法だろう。
有効帯域幅の求め方
ここで、有効帯域幅の値を求める具体例を示すことにする。まずは、振幅の最大許容誤差を決める要因について考えてみる。ここでは、アナログ信号ラインの終端がA-Dコンバータへの入力となるアプリケーションを例にとる。この場合、最終的にはA-Dコンバータの分解能が信号の誤差に大きくかかわることになる。例として、許容最大誤差がA-Dコンバータの分解能の1/2(1/2LSB)であるとしよう。そうすると、A-Dコンバータの分解能が高くなれば、許容最大誤差は小さくなる。表1に、A-Dコンバータの分解能が8〜22ビットの場合に1/2LSBがどのような大きさになるのかを示した。1/2LSBの大きさは、フルスケールを1として、以下の式で計算できる。
上式において、ERRORはA-Dコンバータにおける1/2LSBの大きさ、ADC_RESOLUTIONはA-Dコンバータの分解能を表す。
周波数応答が単極である場合、ゲイン誤差の周波数特性の評価には、正規化のための単極関数を利用するとよい。この単極関数では、閉ループゲインの−3dB周波数に相当する極の周波数fCを1Hzとし、ゲインは1倍(0dB)であるとする(図1)。この関数を利用すれば、ゲイン誤差が所望値以下に収まる周波数を簡単に計算できる。その計算結果から、閉ループゲインの−3dB帯域幅に対する比率として有効帯域幅が求まる。
ここで、−3dB周波数でのゲイン誤差が約30%であることと、少ないゲイン誤差を求める場合、広い帯域幅は得られないことを確認しておこう。
表2は単極関数を用いて計算したゲイン(GAIN)、ゲイン誤差(GAIN_ERROR)の例である。この表において、左端の列は周波数fを表す。これらの各周波数に対し、以下の式(2)、(3)、(4)から計算される値が左端から2〜4番目の列の値だ。
次のステップは、上記の結果を基に、使用するA-Dコンバータの分解能の1/2LSBに相当するゲイン誤差が発生する周波数を求めることである。式(4)と式(1)が等しいと置いた結果得られる次の式(5)を使用すれば、ゲイン誤差が1/2LSBになる周波数が計算できる。
表1と式(5)を用いた計算結果を表3に示す。この表において、右端の列はゲイン誤差がA-Dコンバータの1/2LSBに等しくなる周波数である。これより低い周波数でのゲイン誤差は1/2LSBより小さくなる。すなわち、この周波数までの帯域幅が、使用するA-Dコンバータに対する有効帯域幅だということである。
例えば、10ビットのA-Dコンバータに信号を送るオペアンプの有効帯域幅は−3dB周波数の0.03126倍に位置し、14ビットのA-Dコンバータを利用する場合の有効帯域幅は−3dB周波数の0.007813に位置することになる。オペアンプの閉ループゲインにおける−3dB周波数を100kHzとすると、有効帯域幅は10ビットのA-Dコンバータでは31.3kHz、14ビットのA-Dコンバータでは7.81kHzになるということだ。この結果から、オペアンプの有効帯域幅は−3dB周波数よりもかなり低くなることがわかる。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
記事ランキング
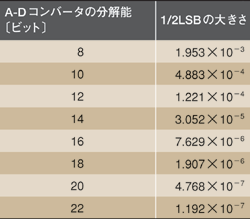
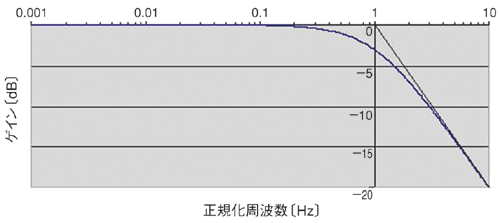 図1 正規化に用いる単極関数
図1 正規化に用いる単極関数 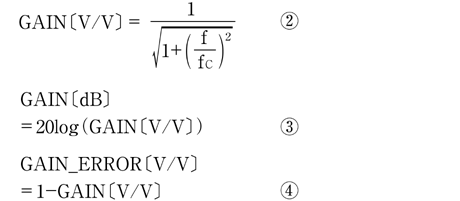
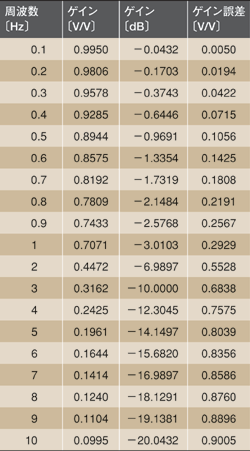 表2 正規化した周波数とゲイン誤差
表2 正規化した周波数とゲイン誤差