信号線直下のギャップが及ぼす影響:Signal Integrity
高速信号を扱うプリント配線板(以下、基板)において、信号配線下のグラウンド面にギャップがあると、思わぬ問題に遭遇することになる。筆者は電磁波干渉(EMI:Electromagnetic Interference)の問題を専門とするコンサルタントであるが、その経験の中で、高速信号を扱う基板の基準層(いわゆるベタグラウンド層と電源層)のギャップをまたぐ信号配線が存在し、それがEMIの原因となっていたというケースに何度も遭遇した。そうした経験から、基板設計時に行うトラブルシューティングにおいては、まず最初に基板の裏から光を当てて、問題になりそうなギャップが存在しないことを確認するようにしている。光を当てるというのが、基板上で問題となる配線を見つけ出すちょっとしたコツだ。もちろん、この方法ではすべての層を突き抜けたギャップしか見えないのだが、意外にも、この簡単な方法が何度も役に立ってきたのである。
基板に信号線を横切るギャップがあると、その点で信号線のインピーダンスが不連続になる。この不連続性により、信号エネルギーの一部が信号源側に反射する。ギャップで反射する成分には入射信号の中の高周波成分が多く含まれる。こうしたメカニズムによって、ギャップを通過した後の信号は立ち上がりがなまったものになる。
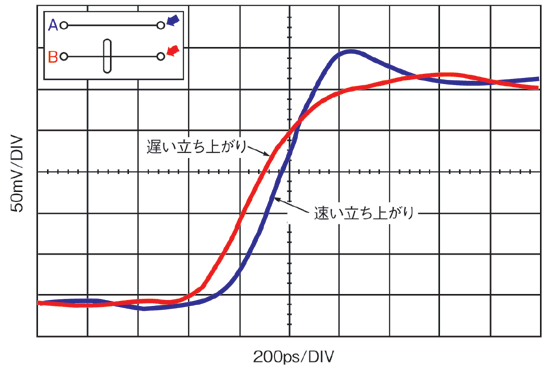 図1 プリント配線板のギャップが高速信号に及ぼす影響 ギャップを横切る信号パターン(B)からの出力は、ギャップのない信号パターン(A)からの出力に比較して立ち上がりが低速になる(時間軸は調整していない)。http://emcesd.com/tt2005/tt010105.htmより転載。
図1 プリント配線板のギャップが高速信号に及ぼす影響 ギャップを横切る信号パターン(B)からの出力は、ギャップのない信号パターン(A)からの出力に比較して立ち上がりが低速になる(時間軸は調整していない)。http://emcesd.com/tt2005/tt010105.htmより転載。筆者は、このような現象を確認するための実験用基板を用意した。その基板の表面層には、図1の左上に示すように、長さ約15cmの2本の直線信号線パターンA、Bを引いた。使用した基板は、信号‐グラウンド‐電源‐信号の一般的な4層構造を持つ。パターンAは特性インピーダンスが50Ωのマイクロストリップ構造である。このパターンは、全体がベタグラウンド層のすぐ上の信号層(表面)にある。パターンBも同一の構造だが、1カ所、基板に存在するギャップを横切っているところがある。そのギャップは幅が5cmの、狭く、深い切り込みである。この切り込みは、ベタグラウンド層と電源層の両方にわたっている。
各パターンに対して、オシロスコープの補助出力から信号を入力し、それぞれの出力を観測した結果が図1の波形である。この図から、各出力波形の立ち上がり時間がそれぞれ300ps、400psと異なっていることがわかる。立ち上がりの速いほうがギャップのないパターンAからの出力である。ギャップの幅が現状よりもっと長くなると、より一層顕著な違いが現われる。
この立ち上がり時間の違いは2つの観点から説明できる。1つは、ギャップによってインピーダンスの不連続性が生じ、それによって反射が発生したということである。もう1つは、(この実験では回路の規模の点で簡略化し過ぎている恐れがあるが)集中定数回路としての観点である。集中定数回路として見れば、信号がパターンBを伝搬する際、パターンを流れる電流と同じ値で反対向きの電流がグラウンド層を流れる。信号がギャップに到達すると、グラウンド層を流れる電流はギャップの両端を回り込んで流れることになる。グラウンドの電流がパターンから離れたところを流れ、パターンを流れる信号の電流との間に距離が存在することになるのでインダクタンスが生じる。このインダクタンスによるフィルタ効果によって、入力信号の高周波成分が減衰することになる。
いずれのメカニズムによるとしても、信号波形の立ち上がり/降下がなまると、さまざまな好ましくない問題が引き起こされる(ただし、信号波形がなまることで、グラウンドバウンスが減少し、EMIの問題が軽減されることもある)。基板レイアウトの問題点を分析する際には、基板にギャップが存在しないかどうか確認してみてほしい。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
記事ランキング



